本記事では、情報処理技術者試験の高度区分のひとつプロジェクトマネージャ試験対策の一環として、個人的に役立った書籍を紹介します。
簡単に概要について触れておきます。
プロジェクトマネージャとは、
高度IT人材として確立した専門分野をもち、組織の戦略の実現に寄与することを目的とするシステム開発プロジェクトにおいて、プロジェクトの目的の実現に向けて責任をもってプロジェクトマネジメント業務を単独で又はチームの一員として担う者
https://www.ipa.go.jp/shiken/kubun/pm.html
とされています。
試験は「午前Ⅰ」「午前Ⅱ」「午後Ⅰ」「午後Ⅱ」の4つの関門があります。
このうち、「午前Ⅰ」「午前Ⅱ」「午後Ⅰ」については、下位区分である「応用情報処理技術者」と同等、もしくはやや難しい程度の難易度であり、過去問を中心に知識と論点を整理していけば、おのずと合格ラインに達することが可能です。
一方で、「午後Ⅱ」の論述は性質が異なり、150分で最低2500字程度を論述する形式で、与えられたテーマに対して経験を交えながら論述を展開していく必要があります。
毎回どのような論点がテーマになるかは分からず、直近の旬なテーマが出題されることもあります。
一つに決まった答えが存在するわけでもないため、過去問のみでは対応が難しいです。
「午後Ⅱ」の対策としては、汎用性が高く書けるネタを複数準備しておき、それらを出題されたテーマに対して柔軟に適用する練習を積んでおくことが有効です。
本記事では、そうしたプロジェクトマネージャ試験の対策向けに、
①基礎知識
②論述ネタ
③論述の書き方
の3つのテーマについて書籍を紹介していきます。皆さんの学習の助けになれば幸いです。
①基礎知識
1. ALL IN ONE パーフェクトマスター プロジェクトマネージャ
概要
本書はTAC情報処理講座が長年培った合格ノウハウを凝縮し、午前Ⅱから午後Ⅱまで試験全体を一冊でカバーするオールインワン教材です。
特に注目すべきは、午後Ⅱ論述のための「ステップ法」。答案を構造化して展開するトレーニングにより、論理的で説得力のある解答を書く基礎力を養えます。
また、午後Ⅰの長文問題に強くなる「三段跳び法」や、過去問を徹底分析した演習問題も収録されており、実戦力を段階的に鍛えられる構成になっています。
さらに、午前Ⅱ・午後Ⅰ対策を通じて基礎知識を整理できるため、最終的に午後Ⅱに集中できる学習環境を整えられる点も大きなメリットです。
プロマネ試験に挑戦するあなたにとって、合格への道を効率的に切り拓く一冊といえるでしょう。
こんな人におススメ
これからプロジェクトマネージャ試験に挑戦する方の多くが、「論述試験の準備をどうすればよいのか分からない」と悩まれています。
午後Ⅱは知識だけでなく、筋道立てて書く力が必要であり、自己流ではなかなか成果が出にくい分野です。
本書はその課題を解決するために、論述構築の方法論「ステップ法」を提供しています。
答案を分解して組み立てるトレーニングにより、試験本番でも落ち着いて論理的な解答を展開できるようになります。
さらに、午後Ⅰの長文読解に強くなる「三段跳び法」や、午前Ⅱの知識整理演習が組み込まれているため、学習全体を通じて効率的に基礎固めが可能です。
結果として「午後Ⅱに集中できる学習環境」を作り出せる点は、初学者にとって特に大きな武器となるでしょう。
学びのポイント
- プロジェクトマネージャ試験の出題傾向とは具体的にどのようなものなのか?
- 午後Ⅱ試験で高得点を取る論述答案は具体的にどのように作るのか?
- 「ステップ法」によって論理的な論述をどのように展開できるのか?
- 午前Ⅱと午後Ⅰの知識整理が午後Ⅱ対策にどうつながるのか?
- 論述試験で失敗しやすい受験生の共通点はなぜ生じるのか?
まとめ
プロジェクトマネージャ試験に挑むとき、多くの受験生が直面する最大の壁は午後Ⅱの論述試験です。知識を持っていても、それを論理的に整理して答案に落とし込むのは簡単ではありません。
本書『ALL IN ONE パーフェクトマスター プロジェクトマネージャ』は、その課題を解決するために、独自の「ステップ法」を通じて論述の基礎力を養い、試験全体を網羅するカリキュラムで効率的に知識を整理できる構成となっています。
午前Ⅱや午後Ⅰで基礎を固めながら、最終的に午後Ⅱに集中できる学習環境を整えられる点は、これから受験に挑む初学者にとって大きな助けとなるでしょう。
一方で、分厚い一冊を独学で計画的に進める自己管理力は求められます。
しかし、それらを理解した上で使い込むならば、本書は試験合格の強力な道しるべとなります。
あなたが「次の秋試験で必ず結果を出したい」と本気で思うなら、この教材を手に取り、合格に必要な基礎力と論述力を今から積み上げてみてはいかがでしょうか。
2. PMBOK対応 童話でわかるプロジェクトマネジメント[第2版]
概要
プロジェクトマネージャ試験の学習を進める際、多くの受験生がつまずくのが「PMBOKの内容をどう具体的に理解するか」という点です。
体系そのものは整然としていますが、初学者にとっては抽象度が高く、実務と結びつけにくい部分も少なくありません。
そこで役立つのが『PMBOK対応 童話でわかるプロジェクトマネジメント[第2版]』です。
本書は「三匹の子ブタ」「ウサギとカメ」「桃太郎」など誰もが知っている童話をモチーフに、プロジェクトマネジメントの要点を親しみやすく学べる入門書です。
特に第2版で第7版対応になった点は見逃せません。
近年の試験傾向を踏まえた最新PMBOKに準拠しつつ、抽象的な用語を「物語の教訓」に置き換えることで、PM知識体系の全体像を感覚的に捉えることができます。
また、章末には「PMBOKへの橋渡し」と題した解説があり、童話で得たイメージと正式な用語体系をリンクさせる工夫も施されています。
プロジェクトマネージャ試験を控え、まずはPMBOKの俯瞰的理解を得たい方に最適の一冊といえるでしょう。
こんな人におススメ
「PMBOKを通読してもなかなか頭に入ってこない」──これは多くの受験生に共通する悩みです。
試験勉強を始めたものの、抽象的な知識領域やプロセス群の羅列に苦戦し、「実感を持って理解できない」と感じる方は少なくないでしょう。
本書はそうした課題を解消するために、童話という比喩を用いてPMBOKの概念を具体的なイメージとして提示します。例えば「三匹の子ブタ」では堅実な段取りの重要性を、「ヘンゼルとグレーテル」ではリスク管理を、といった具合に物語と概念を結びつけることで、知識を感覚的に整理できる仕組みになっています。
これにより、試験対策としてPMBOKを「俯瞰する第一歩」を効率的に踏み出すことが可能です。
ただし注意点もあります。物語に抽象化されているため、現場での具体的なプロジェクト事例を得る目的には適していません。
したがって「PMBOK全体像を把握する」「試験勉強の最初の足掛かりを得る」といった用途には強く推奨できますが、実務に直結する応用事例を求める方には物足りない可能性が高いです。
学びのポイント
- プロジェクトの「段取り」とは具体的にどのような考え方なのか?
- ゴール設定をチームで共有するにはなぜ「方向性の一致」が重要なのか?
- チームメンバーを仲間として結束させるにはどのように行動すべきか?
- リスク管理を行う際に、事前準備と対応策の両立はどう考えるべきか?
- ネガティブな状況に直面したとき、どのように周囲を巻き込めばよいのか?
まとめ
『PMBOK対応 童話でわかるプロジェクトマネジメント[第2版]』は、PMBOKの全体像を掴むための入門書として大きな役割を果たしてくれます。
童話を通じて学ぶことで、難解な概念も具体的なイメージとして頭に残りやすく、試験勉強の序盤で「理解の取っ掛かり」を掴むことができます。
一方で、現場に直結するリアルな事例は得にくいため、実務力強化を目的とする場合は別の教材との併用が望ましいでしょう。とはいえ、PMBOKの俯瞰理解を効率的に進めたい初学者にとっては、非常に心強い相棒となります。
あなたがもし「試験勉強を始めたばかりで、まずはPMBOKを全体的に掴みたい」と考えているなら、この一冊を入り口として学習をスタートするのが賢明な選択といえるでしょう。
3. 図解まるわかり PMO・PMのきほん
概要
プロジェクトを推進する上で欠かせないのが PM(プロジェクトマネージャ) と PMO(プロジェクトマネジメントオフィス) の存在です。
しかし、両者の立場や役割の違いを明確に説明できる人は意外と多くありません。
特にプロジェクトマネージャ試験に臨む際、この違いをきちんと理解しているかどうかが、答案の質を大きく左右します。
『図解まるわかり PMO・PMのきほん』は、この両者の立ち位置を DXプロジェクト/ITプロジェクトという2つの軸 から整理し、図解とともに体系的に学べる入門書です。
見開きごとに1テーマを扱う構成で、PMとPMOの役割の重なりや補完関係を比較しながら解説しているため、試験勉強において「誰が何を担うのか」をクリアに理解できます。
さらに「DXは型が定まらない」という現実を踏まえた上で、ITプロジェクトとの共通原則を示している点も実践的。
プロジェクトマネージャ試験対策として、PMとPMOの位置づけを整理しておきたい方にとって、知識の整理と試験対応力を高める一冊といえるでしょう。
こんな人におススメ
プロジェクトマネージャ試験を控えている方の多くが、「PMとPMOの違いをどう説明すればいいのか」「試験問題でどちらの役割を前提に書けばよいのか」と悩まれます。
答案で曖昧な理解がにじむと減点対象になりやすく、合否に直結することも少なくありません。本書はまさにその弱点を補う内容です。
PMが担う「意思決定と成果責任」と、PMOが担う「環境整備と標準化支援」を対比させながら、具体的な活動内容を図解で整理してくれます。
DXとITという異なる性質のプロジェクトを題材にしているため、抽象的な概念だけでなく実務で想定される状況をイメージしやすいのも特徴です。
さらに、章ごとに「PM/PMOが工程別に何をするのか」がまとめられており、試験で答案を組み立てる際の基盤として役立ちます。
したがって「試験対策の視点で、PMとPMOの違いをしっかり理解して整理したい」というニーズに対しては最適ですが、「現場のベストプラクティスを深掘りしたい」方には別の参考書との併用が望ましいでしょう。
学びのポイント
- PMOとPMはそれぞれ具体的にどのような役割を担うのか?
- プロジェクトマネージャの立場として意見を述べるため、PMとPMOをどう区別して理解すべきか?
- ITプロジェクトとDXプロジェクトでは役割分担にどのような違いがあるのか?
- 工程ごとにPMが主体となる活動は具体的に何か?
- PMの成果責任とPMOの支援責任はなぜ区別して考える必要があるのか?
まとめ
プロジェクトマネージャ試験では、単に知識を暗記するだけでは合格できません。
特にPMとPMOの役割の違いを正確に理解し、答案で適切に表現できるかどうかは、試験官が評価する大きなポイントです。
『図解まるわかり PMO・PMのきほん』は、この点を補強するための格好の教材です。DXとITという異なる舞台での両者の役割を比較しながら整理できるため、知識を体系的に俯瞰することが可能です。
また、図解形式で要点がまとまっているため、試験直前の総復習にも良いです。一方で、実務的なケーススタディを豊富に学びたい人には情報量が物足りなく感じる部分もあります。
あなたがもし「PMOとPMの立場の違いが曖昧かもしれない」と感じているなら、この一冊を通じて整理し、自信を持って答案に反映させる準備をしてみてはいかがでしょうか。
②論述ネタ
1. プロジェクトマネジャーの決断 富士通の現場から
概要
本書は富士通のPMコミュニティが実際の現場で直面した問題を題材に、プロジェクトマネージャとしてどのような決断をすべきかを4択形式で問いかけます。
スコープ、品質、人材、コミュニケーション、リスク、コスト、納期など、試験でも頻出する領域をカバーしつつ、解答は「推奨解答」という形で現場の実務に基づいて提示されます。
理論的な唯一解ではなく、あくまで「現場でどう判断したか」を重視している点がユニークであり、受験勉強においては「模範的な答えと実際の判断が異なる理由」を考える絶好の素材となります。
プロジェクトマネージャ試験対策を進める中で、理論を超えた現場感覚を養いたい方にとって、一読の価値がある実践的な教材です。
こんな人におススメ
試験勉強をしていて、「理論は理解したけれど、実際のプロジェクトではどう適用されるのだろう」と悩んだ経験はありませんか?本書はまさにその疑問に答えてくれます。
例えば「品質を守るための判断がコストや納期にどう影響するか」「トラブルを未然に防ぐリスク管理はどう実践されているか」といった具体的な場面をケースとして提示し、選択肢を通じて自分なりの決断を試すことができます。
こうした演習を繰り返すことで、机上の空論ではなく「現場で通用する判断力」を鍛えられるのが本書の最大の強みです。
一方で注意が必要なのは、解答があくまで富士通の現場での推奨判断に基づいている点です。必ずしもPMBOKや試験の理論解答と一致するわけではありません。
したがって、理論の整理には別のテキストを用い、本書は「実践的な判断訓練」として並行活用すると効果的でしょう。
学びのポイント
- プロジェクトのスコープを守るために、現場ではどのような判断が求められるのか?
- コミュニケーション不足が招くリスクにどう対応すべきなのか?
- リスク管理で「防火」と「消火」の違いをどう認識すべきか?
- プロジェクトはなぜ計画通りに進まないのか、その時PMはどう動くのか?
- ステークホルダーを協力者に変えるために、どんなアプローチが有効なのか?
まとめ
プロジェクトマネージャ試験の合格に必要なのは、理論的な知識を正しく理解するだけではありません。
その知識をベースにしつつ、現場でどう意思決定するのかを考え抜く力が求められます。『プロジェクトマネジャーの決断 富士通の現場から』は、まさにその訓練に最適な教材です。
現場で起きたリアルな問題とその対応策を通じて、自分ならどう決断するかを疑似体験でき、判断力の幅を広げられます。
ただし注意点として、解答はあくまで富士通の現場での推奨判断であり、必ずしも試験理論と一致しない場合があります。そのため、試験勉強では「理論書」と「本書」を補完的に使うことが不可欠です。
理論を頭に入れた上で、本書を使って「現場ならどう動くか」を考えることで、より深い理解と実践的な解答力を身につけられるでしょう。
あなたがもし「理論と実務の橋渡しをしたい」と考えているなら、この一冊を試験対策の学習に組み込み、現場感覚と判断力を磨いてみてはいかがでしょうか。
2. プロジェクトのトラブル解決大全 小さな問題から大炎上まで使える「プロの火消し術86」
概要
プロジェクトマネージャ試験に臨む皆さんにとって、最も難しい壁の一つは「机上の理論を現場感覚と結びつけて、説得力ある論述答案を書くこと」ではないでしょうか。教科書や過去問演習を通じて基本的な知識やフレームワークを身につけても、いざ答案に落とし込むと「実例の裏付け」が弱く、抽象的な表現に留まってしまうことが少なくありません。そんな受験生に強くお勧めしたいのが、木部智之氏の著書『プロジェクトのトラブル解決大全』です。
本書は、著者がIBM時代をはじめとした数多くの炎上プロジェクトを収束させてきた経験を凝縮した、まさに「火消し事例集」です。序章からクロージングまで、プロジェクトがトラブルに陥った際のセオリーが実践的に整理されており、単なる理論書ではなく、泥臭い現場でどう人を動かし、計画を立て直し、成果に結びつけるのかが具体的に描かれています。
特に注目すべきは、「モチベーションは上げるのではなく戻す」「炎上中の管理は3つだけ」といった、現場経験から導かれた独自の視点です。試験論述では、こうした実例に基づくフレーズを答案に盛り込むことで、単なる知識披露ではなく「実務家らしい判断力」を表現することが可能になります。
プロジェクトマネージャ試験は、合格後に実際の現場でリーダーシップを発揮できるかどうかを問う試験でもあります。本書を読むことで、答案作成力を高めるだけでなく、将来の実務における対応力まで鍛えられるはずです。
こんな人におススメ
プロジェクトマネージャ試験の論述で悩む多くの受験生に共通する課題は、「現場の臨場感を答案に落とし込むことができない」という点です。
フレームワークや標準的な知識は学習済みでも、答案がどこか机上の空論に見えてしまう。その差は、実例に基づく説得力の有無にあります。こうした悩みを抱える方にこそ、『プロジェクトのトラブル解決大全』は大きな助けとなるでしょう。
本書は、炎上プロジェクトをいかに立て直すかという泥臭い局面を正面から扱っています。「状況把握」「原因特定」「リカバリプラン策定」などの手順は、試験で問われるプロセスそのものです。
これを実務経験豊富な著者の視点から読むことで、答案に盛り込む「リアリティのある施策」の幅が一気に広がります。特に、メンバーモチベーションの回復やリーダーシップの取り方など、単なる理論では説明しにくい要素を具体例として学べるのは貴重です。
さらに、本書の良さは「抽象論ではなく行動レベルで示されていること」です。
例えば「犯人探しは活用に変える」「リカバリ中は管理項目を3つに絞る」といった示唆は、上手く言い換えればそのまま答案のキーフレーズとして応用できそうです。こうした記載を盛り込むことで、試験官に「実務家の思考を持っている」と印象づける力を持つでしょう。
ただし注意点もあります。本書の事例は主にIT・システム開発案件をベースにしているため、全業界にそのまま適用できるわけではありません。
また、解決手法がやや著者流で整理されている部分もあり、標準PMBOKとの対応を自分で補う必要があります。
そのため、知識の土台がまだ固まっていない初学者よりは、一定の基礎を学んだ上読むことをおススメします。
学びのポイント
- プロジェクトトラブル解決のセオリーとは具体的にどのようなものなのか?
- なぜ多くの人がプロジェクトのスタート段階でつまずいてしまうのか?
- 現場の状況把握はどのように効率的に行えば良いのか?
- 真因を特定しリカバリプランを策定する際に重要な手順は何なのか?
- 炎上中のプロジェクト管理を「3つだけ」に絞るとは具体的にどういうことなのか?
まとめ
プロジェクトマネージャ試験の論述に挑む皆さんにとって、最も重要なのは「現場に即したリアリティある答案を書くこと」です。理論をなぞるだけの解答では、実務家審査員の心に響きません。
その差を生むのは、実際にトラブルと向き合った経験や、そこで得られた教訓をいかに自分の言葉で語れるかという点に尽きます。『プロジェクトのトラブル解決大全』は、まさにその材料を提供してくれる一冊です。
本書を読むと、プロジェクトの炎上をどう収束させるか、メンバーをどう再び動かすか、計画をどう立て直すかといった「生の知恵」が数多く示されています。
答案作成時に「なぜこの施策が有効なのか」と説明する際、著者の経験談に裏付けられたフレーズを取り入れるだけで、解答の説得力が大きく高まります。試験勉強の段階で現場感覚を得ることは難しいですが、この本を通じて間接的に経験を吸収できるのは大きなアドバンテージです。
もちろん、すべての事例がそのまま答案に使えるわけではなく、IT系中心の内容を自分の試験答案にどう応用するかを考える工夫は必要です。
しかし、その過程こそが論理を実践に橋渡しする練習となり、本番での解答力を磨いてくれます。
もしあなたが「答案がどうしても抽象的に見える」「現場感をもっと強めたい」と感じているなら、この一冊を取り入れてみてください。
試験合格を目指す上での力強い相棒になるだけでなく、将来あなたが実際にプロジェクトを任されたときの心強い支えともなるはずです。
3. 予定通り進まないプロジェクトの進め方
概要
プロジェクトマネージャ試験に挑む受験生にとって、論述答案を作る際の大きな課題は「理論を並べるだけで終わってしまう」という点です。
知識やフレームワークは十分に理解していても、それを答案にどう落とし込み、実務家審査員に説得力を持って伝えるかが勝負になります。特に現場経験が浅い方にとっては、「リアルなエピソードや具体策」を盛り込むことが難しく、答案が抽象的になりがちです。
この課題を解決する一助となるのが、前田考歩氏と後藤洋平氏の共著『予定通り進まないプロジェクトの進め方』です。
本書は、プロジェクトが必ずしも計画通りに進まないという現実を前提に、その上でどう対応していくかを「編集」という新しい視点で解き明かしています。
単にガントチャートや進捗管理に頼るのではなく、状況に応じてプロジェクトそのものを編集し直す姿勢を強調しているのが特徴です。
特にユニークなのが「プロジェクト譜(プ譜)」というツール。これはプロジェクトを可視化し、変化に応じて柔軟に修正していけるもので、論述答案に取り入れれば「独自の実例」として活用できます。
さらに、感想戦という振り返りの方法論も紹介されており、答案に「次の改善策」を盛り込む際のヒントになります。
つまり本書は、現場経験が少ない受験生でも「実例に基づいた論述」を組み立てるための貴重な素材集です。
試験対策だけでなく、実際にプロジェクトを率いる場面でも役立つ知恵が凝縮されており、論述力と実務感覚を同時に磨ける一冊と言えるでしょう。
こんな人におススメ
プロジェクトマネージャ試験の論述問題に取り組むとき、「自分の解答がどうしても理論先行になってしまう」「現場感覚のある施策を盛り込みたいが、経験が足りない」という悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
特に実務経験が浅い受験生にとっては、答案に説得力を持たせるための「生きたネタ」を探すことが大きな課題です。そんなとき、『予定通り進まないプロジェクトの進め方』は有効な武器となります。
本書は、プロジェクトが計画通りに進まないことを前提に、その状況をどう乗り越えるかを「編集」の発想で解き明かします。
計画のずれや想定外の事態に直面したとき、単なる進捗管理ではなく、全体を柔軟に書き換えていく視点は、答案に盛り込むことで非常にリアリティを帯びます。特に「プロジェクト譜(プ譜)」という可視化ツールは、問題把握や軌道修正の論述において、独自性ある具体策として活用できるでしょう。
さらに、終了後に「感想戦」を行い、プロジェクトを振り返るという発想もユニークです。論述答案に「次に活かす改善策」を盛り込む際、この考え方を引用すれば、解答に深みを与えることが可能です。
つまり、現場経験が少なくても、本書を通じて得た事例を答案に応用すれば、経験豊富な受験生に劣らない実践的な回答ができるようになります。
ただし注意すべき点もあります。本書は編集的な切り口を重視しているため、PMBOKの体系的な知識とはやや異なる部分があります。そのため、知識の基盤がまだ固まっていない段階で読むと混乱する可能性もあります。
したがって、まず標準的な知識を身につけ、その上で本書を補助的に活用するのが望ましいでしょう。
学びのポイント
- 想定外を前提にした進め方とはどのようなものなのか?
- プロジェクト工学の3つの法則とは何を意味するのか?
- プロジェクト譜(プ譜)を使うことでプロジェクトをどう可視化・修正できるのか?
- 「編集」という発想はプロジェクト進行にどう活きるのか?
- 感想戦の着眼点とは何であり、次にどう役立つのか?
まとめ
プロジェクトマネージャ試験の論述では、いかに具体的で説得力ある解答を書けるかが合否を分けます。しかし、現場経験が少ない受験生にとって、その「実例」を答案に盛り込むのは難しい課題です。
そこで役立つのが『予定通り進まないプロジェクトの進め方』です。本書は、プロジェクトが常に順調に進むわけではないという現実を出発点とし、そこからどう軌道修正を図るかを「編集」というユニークな視点で解説しています。
特に「プロジェクト譜(プ譜)」を用いた可視化や、「感想戦」という振り返りの手法は、論述答案に盛り込めば他の受験生と一線を画す内容になります。
単なる知識暗記にとどまらず、プロジェクトの動態を柔軟に捉える力を養えるのは、本書ならではの強みでしょう。これらを答案に反映させることで、「現場を理解している」という印象を与え、評価を高めることができます。
もちろん、PMBOKなどの体系的な知識に直接対応しているわけではないため、まずは標準的な理論を押さえた上で活用するのが理想です。
しかし、この一冊を手元に置き、答案作成の練習過程で「実例の引き出し」として参照すれば、現場経験の不足を補い、説得力を強化することが可能です。
試験本番で「理論だけでは浅い」と感じさせないために、あなたの答案にリアリティを加える一冊として、本書を活用してみてはいかがでしょうか。
合格への確かな後押しとなるだけでなく、合格後に実務でプロジェクトを率いる際の支えにもなるはずです。
③論述の書き方
1. プロジェクトマネージャ試験 午後I記述・午後II論述の徹底対策
概要
プロジェクトマネージャ試験における最大の難関の一つが午後Ⅱ論述です。限られた時間の中で、課題文を読み取り、自らの経験や知識を踏まえて一貫性のある論文を構成することは、多くの受験生にとって大きな挑戦となります。
知識だけでは突破できず、「論理の流れ」「表現力」「実務感覚」の3点を兼ね備えた答案が求められるため、自己流の勉強法では壁にぶつかりやすいのが現実です。
そんな受験生にとって心強い味方となるのが、広田航二氏の『プロジェクトマネージャ試験 午後I記述・午後II論述の徹底対策』です。
本書は、午後Ⅰと午後Ⅱを体系的につなぐ総合対策書であり、とりわけ午後Ⅱの論述に重点を置きながら、思考法から答案構成までを段階的に解説しています。
特に価値があるのは「論文作成の実例」です。過去問を題材に実際の答案が提示されており、単なる解説ではなく「このように論理を組み立てる」という具体的なイメージを掴むことができます。
さらに、モジュール体系という独自の準備法が紹介されており、設問が変わっても対応できる「型」を自分の中に構築できる点は他の参考書にはない強みです。
また、答案の自己評価方法や、本番当日の時間配分、注意点まで丁寧に触れられているため、受験準備の全プロセスをこの一冊で網羅できます。
午後Ⅱの突破に不可欠な「思考の型」と「論文作成力」を養う場として、本書は非常に実践的かつ有効な教材といえるでしょう。
こんな人におススメ
午後Ⅱの論述に苦手意識を持つ受験生は少なくありません。「論理がまとまらない」「経験をどう書けばいいかわからない」「時間内に形にできない」といった悩みは、過去問演習だけではなかなか解消できないものです。こうした課題を抱えている方にこそ、『プロジェクトマネージャ試験 午後I記述・午後II論述の徹底対策』は強力な助けとなります。
本書の最大の特徴は、論述試験を「思考法」から体系的に学べる点にあります。課題文をどう読み解き、設問の狙いをどのように捉え、どんな枠組みで答案を構築するのかというプロセスが、具体的な手順として解説されています。自己流では気づきにくい「試験官の視点」を踏まえた書き方を習得できるため、論述の完成度が飛躍的に高まります。
また、実際の過去問に対する論文例が提示されており、「このように展開すればよい」という具体像を得られるのも大きな利点です。
現場経験が豊富でなくても、自分の知識や疑似体験を答案に落とし込む手がかりをつかむことができます。さらに、モジュール体系を準備しておけば、問題の切り口が変わっても応用が効き、安定して答案を作れるようになります。
ただし、本書の内容は分量が多く、初学者にはやや負荷が高いかもしれません。また、解答の方向性や手法が著者のスタイルに基づいているため、必ずしも自分に合うとは限らず、取捨選択しながら活用する必要があります。
その点を理解した上で、午後Ⅱ論述を徹底的に攻略したい中級以上の受験生には、まさにうってつけの一冊です。
学びのポイント
- 問題文を読み込む際にどのような視点を持つべきなのか?
- 設問の意図を的確に分析するためには何を意識すべきなのか?
- 論文の構成を組み立てる際に押さえるべき基本手順とは何なのか?
- 過去問の論文例からどのように答案の型を学び取れるのか?
- モジュール体系を作ることでどんな効果が得られるのか?
- 論文の自己評価はどのような観点から行えば良いのか?
- 本試験当日に時間配分を工夫するためにはどうすればよいのか?
- 午後Ⅰと午後Ⅱを連動して学ぶことにどんな意味があるのか?
まとめ
プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅱ論述は、多くの受験生にとって最も高い壁です。論理をどう展開するか、経験をどう答案に落とし込むか、そして限られた時間でどう仕上げるか。
この3つを克服するためには、単なる知識ではなく「答案作成の型」と「実例に基づいた思考法」が不可欠です。
広田航二氏の『プロジェクトマネージャ試験 午後I記述・午後II論述の徹底対策』は、その両方を一冊で学べる点に強みがあります。問題文の読み解き方から答案の構成手順、実際の論文例まで具体的に提示されているため、机上の理論にとどまらず「答案にどう書けばよいか」という最重要ポイントを掴むことができます。
さらに、モジュール体系という準備法を取り入れることで、設問の切り口が変わっても応用できる柔軟な解答力を身につけることが可能です。
もちろん、初学者にとっては分量や内容の密度が負担になる可能性もありますし、著者独自のアプローチをそのまま鵜呑みにするのではなく、自分に合った方法を選び取る姿勢も必要です。
しかし、それを踏まえてもなお、本書は午後Ⅱ対策を総合的に網羅する数少ない教材として非常に価値があります。
もしあなたが「論述で何を書けばよいかわからない」「答案の筋道が立たない」と悩んでいるなら、この一冊を手にとってみてください。午後Ⅱ論述突破の道筋が明確になり、合格への大きな一歩を踏み出せるはずです。
そして、試験を超えた先の実務においても、自信を持って論理を組み立てられる力が養われるでしょう。
2. プロジェクトマネージャ 合格論文の書き方・事例集
概要
プロジェクトマネージャ試験に挑むうえで、多くの受験生が苦戦するのが午後Ⅱ論述です。限られた時間の中で、課題文の趣旨に沿った一貫性ある論文をまとめるのは容易ではありません。知識は十分でも「答案のイメージが湧かない」「書き出しでつまずいてしまう」という声は少なくなく、独学では壁を感じやすい領域です。
そんな課題を克服するために有効なのが、『プロジェクトマネージャ 合格論文の書き方・事例集』です。本書は午後Ⅱ論述に特化し、論文の基本的な構成方法から、時間内に仕上げるための手順までを網羅的に解説しています。特筆すべきは、第2部に収録された 合格論文の事例30本 です。進捗管理・品質管理・費用管理・リスク管理といった多様なテーマを扱っており、受験生はこれらを参照することで、答案の具体的なイメージをつかむことができます。
さらに、巻末にはワークシートや演習課題があり、読んで理解するだけでなく「自分で手を動かしながら学べる構成」になっています。演習を通じて答案の枠組みを体得し、添削やQ&A形式で弱点を補う仕組みが整っているのも特徴です。
この一冊を使えば、論述に必要な「考え方」と「書き方」の両面を鍛えられるだけでなく、実際に試験で出題される多様なテーマへの対応力も身につきます。午後Ⅱ論述を突破するための実践的な教材として、本書は大きな価値を持っています。
こんな人におススメ
午後Ⅱ論述に向けて過去問演習を重ねても、「答案の形が定まらない」「具体例の引き出しが少ない」と感じている受験生は多いのではないでしょうか。
論述試験で求められるのは、単なる知識の羅列ではなく、与えられたテーマに沿って筋の通ったストーリーを展開する力です。そこに多くの受験生がつまずき、合格ラインに届かないまま試験を終えてしまうケースが後を絶ちません。
こうした課題を抱える方にこそ、『プロジェクトマネージャ 合格論文の書き方・事例集』は強くおススメできます。本書は論述試験に特化しており、問題文の趣旨に沿って論文を設計し、時間内に完成させるための技術を体系的に解説しています。
特に大きな特徴は、第2部に収録された 合格論文の事例30本。進捗・品質・リスクなど多様なテーマを扱っているため、答案作成時に「このテーマならこう展開すれば良い」という具体的な指針を得ることができます。
また、巻末のワークシートや演習課題を利用すれば、インプットにとどまらず、自分の答案作成スキルを実践的に磨けます。添削やQ&A形式の内容も盛り込まれているため、独学で行き詰まりがちな部分を補強できる点も魅力です。
一方で、掲載されている事例の一部は古めであり、最新の出題傾向と完全に一致するとは限りません。そのため、あくまで「答案の型」を学ぶ教材と位置づけ、最新の過去問と組み合わせて使うのが効果的です。
また、情報量が豊富なため、初学者には少し負担が大きい可能性もあります。基礎をある程度固めた上級受験生が、本書を軸に演習を重ねることで最も効果を発揮するでしょう。
学びのポイント
- 午後Ⅱ論述試験に合格する論文の基本構成とはどのようなものなのか?
- なぜ問題文の趣旨を正確に把握することが論文合格に直結するのか?
- 時間内に論文を仕上げるためにどのような手順を踏むべきなのか?
- 合格論文30本の事例から具体的にどのような表現を学び取れるのか?
- 進捗管理の論文ではどのように課題と解決策を描けばよいのか?
- 品質管理をテーマにした論文で説得力を高めるには何を強調すべきなのか?
- リスク管理を扱う論文で有効なストーリー展開とはどのようなものか?
- 演習ワークシートを活用することでどのように論述力を強化できるのか?
- 添削やQ&A形式の学習を通じてどのように弱点を補強できるのか?
まとめ
プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅱ論述は、単なる知識暗記では太刀打ちできない試験です。課題文の意図を正しく読み取り、筋道の通った論理を展開し、さらに限られた時間内に答案を完成させる力が問われます。
しかし、実務経験や演習量が不足していると、「どのように書き進めればいいのか」「解答の具体性が足りない」と悩む受験生は少なくありません。
そうした壁を乗り越えるために有効なのが、『プロジェクトマネージャ 合格論文の書き方・事例集』です。本書は論文作成の基本手順を丁寧に解説するとともに、合格論文の実例を30本収録しています。
進捗管理・品質管理・リスク管理といった多様なテーマを網羅しているため、答案に必要な具体性とバリエーションを手に入れることができます。「このテーマなら、こう展開できる」というイメージを掴めることは、独学では得がたい強みです。
さらに、ワークシートや演習問題、添削を前提としたトレーニング要素が盛り込まれているため、読むだけではなく「書いて試す」ことができます。これは、論文作成力を実際に身につけるうえで非常に重要なステップです。
もちろん、掲載事例の一部は古く、最新の試験傾向と完全に一致するわけではありません。そのため、最新の過去問と組み合わせて使う工夫は必要です。しかし、本書で示される「答案の型」を学ぶことで、自分なりのスタイルを確立でき、論述への不安を大きく軽減できるでしょう。
午後Ⅱ論述で自信を持ちたい、答案の形を明確にしたいと考える受験生にとって、本書は頼れる伴走者となります。あなたの論文作成力を確実に一段引き上げ、合格への大きな後押しとなるはずです。
3. やはり僕の論文は間違っていた。
概要
プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅱ論述に挑むとき、多くの受験生が直面するのは「どうして自分の答案が評価されないのか」という疑問です。知識を盛り込み、設問に答えているつもりでも、思ったほど点数につながらない。
そこには、論文試験特有の「心構え」と「書き方の癖」が影響しています。しかし、それを自分一人で気づくのは難しいものです。
そこで役立つのが、左門至峰氏の『やはり僕の論文は間違っていた。』です。本書は、論文試験のノウハウを単に解説するのではなく、小説仕立ての物語形式で描いているのが特徴です。主人公が過去の恋人に宛てた手紙をきっかけに、自分の書いた論文が「間違っていた」と気づき、改善していく過程を追体験できる構成になっています。
そのため、読者は肩ひじ張らずに読み進めながら、自分の答案の欠点や改善の視点を自然と学べます。
本書が伝えるメッセージは明快です。論文試験は特別な文章作成ではなく、日常的なメールや報告書に通じる「相手に伝わる文章」を書くことが本質であるという点です。
小説のストーリーを楽しみながら読むうちに、試験で求められる「正しい心構え」が腑に落ち、自分自身の学習姿勢を見直すきっかけになります。
論文が思うように書けない、答案の出来が不安、そんな悩みを抱える受験生にとって、本書は単なる参考書以上に「心を整える一冊」となるでしょう。
こんな人におススメ
午後Ⅱ論述に取り組む中で、「自分の論文がなぜ評価されないのか分からない」と悩んだことはありませんか。知識を詰め込んで設問に答えているつもりでも、結果が伴わない。その原因は、論文の技術的な不足だけではなく、論文試験に対する心構えや視点にズレがあるケースが少なくありません。
こうした課題を抱える方にこそ、『やはり僕の論文は間違っていた。』は適しています。
本書は、小説仕立ての物語形式で進みます。主人公が自らの失敗を振り返りながら成長していく姿を追体験することで、読者は自分自身の論文を客観的に見直せるようになります。「どこが間違っていたのか」「なぜ伝わらなかったのか」という視点を物語の中で自然に学べるのは、従来の参考書にはないユニークなアプローチです。
論文対策が堅苦しく感じられていた受験生にとっても、物語を楽しみながら学べることで取り組みやすくなるでしょう。
また、本書が強調するのは「論文は特別なものではない」という考え方です。日常のメールや報告書と同じく、読み手に分かりやすく伝えることが本質だというメッセージは、論文試験を必要以上に難しく感じていた方の心理的なハードルを下げてくれます。
ただし、本書は物語をベースにしているため、論文の具体的な書き方や最新の試験傾向に即した対策を詳細に知りたい方には物足りない部分もあります。
そのため、基礎知識や過去問演習と併用し、あくまで「心構えを整え、答案を客観視する」補助教材として活用するのが最適です。
学びのポイント
- なぜ自分の論文が評価されないことに気づけないのか?
- 論文試験において「正しい心構え」とはどのようなものなのか?
- 間違った論文の典型例にはどんなパターンがあるのか?
- 相手に伝わる論文を書くために必要な工夫とは何か?
- 論文を客観視するためにはどんな視点を持てば良いのか?
まとめ
プロジェクトマネージャ試験の午後Ⅱ論述は、知識や経験だけでは突破できない難関です。合格ラインに届かない理由は、論理展開や具体性の不足だけでなく、論文に向き合う心構えや視点にズレがあることが少なくありません。
自分の答案を客観的に見直し、改善点を冷静に捉えることができなければ、どれだけ勉強を重ねても伸び悩むのが現実です。
左門至峰氏の『やはり僕の論文は間違っていた。』は、そんな悩みを抱える受験生に新たな気づきを与えてくれる一冊です。物語形式を通じて、主人公の失敗と成長を追体験できるため、読者自身も「自分の答案を客観的に見る」練習が自然にできます。
また、「論文は特別なものではなく、日常の文章作成の延長」というメッセージは、試験を必要以上に難しく感じていた受験生の心理的ハードルを下げてくれるでしょう。
もちろん、この本だけで論文試験を突破できるわけではありません。物語中心の構成ゆえに、具体的な論文作成の手順や最新の出題傾向を知るには別途の教材が必要です。
しかし、試験勉強における「心構え」と「改善の視点」を整える補助教材として活用すれば、論文対策の基盤をより強固にできます。
もしあなたが「答案を書いてもどこか自信が持てない」「自分の論文をどう改善すべきかわからない」と悩んでいるなら、この本を一度手にとってみてください。
論文試験に臨むうえでの姿勢が変わり、自分の答案を冷静に磨き上げる力がつくはずです!










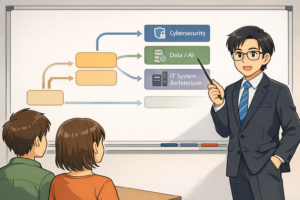
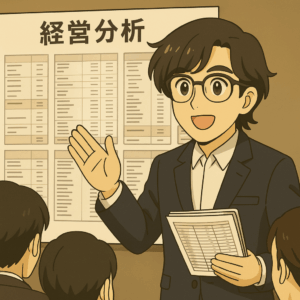
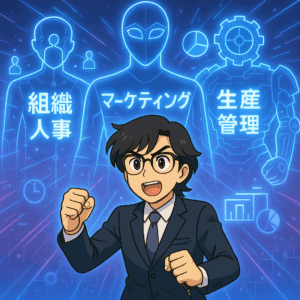
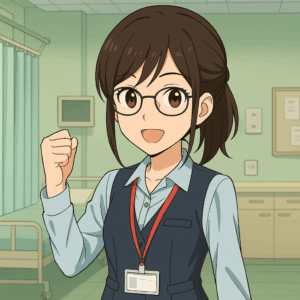


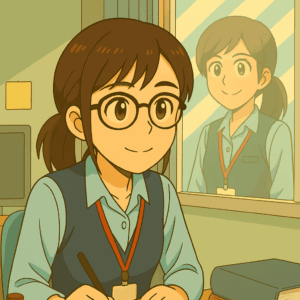
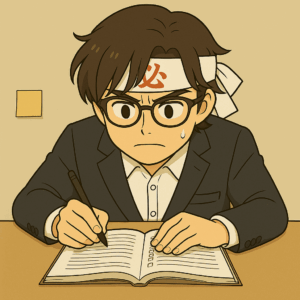
コメント