本記事では中小企業診断士2次試験にフォーカスし、難関と言われる論述試験に対して独学で立ち向かうのに役立つと思われる書籍(参考書含む)9選を紹介します。
本記事では主に、
①事例Ⅰ ~組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例~
②事例Ⅱ ~マーケティング・流通を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例~
③事例Ⅲ ~生産・技術を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例~
の3つのテーマについて書籍を紹介していきます。参考になれば幸いです。
なお、中小企業診断士2次試験に立ち向かうための基礎力を養うのにおススメの書籍については以下でまとめていますので、併せて参照いただけると幸いです。
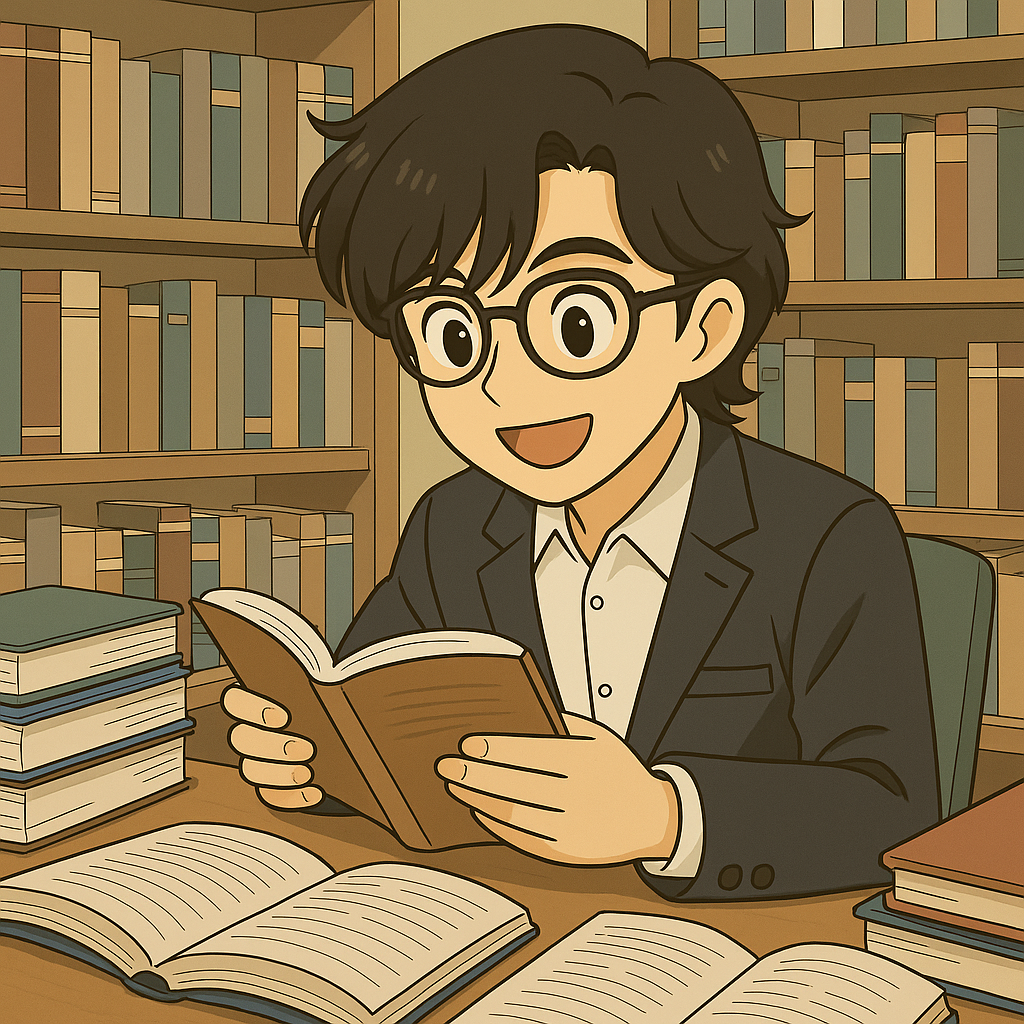
また、実際に演習を行う段階で有用な書籍は以下で紹介しています。合わせて参照いただけると幸いです。
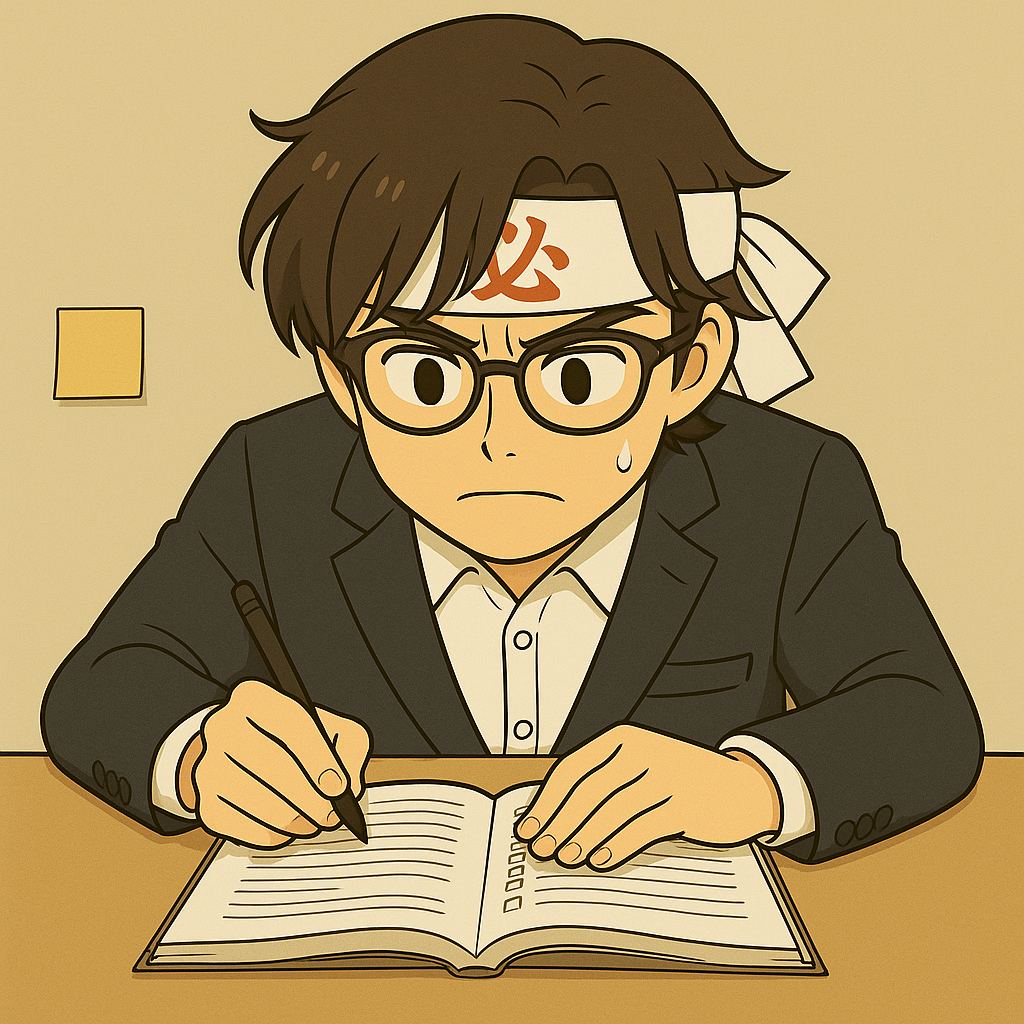
①事例Ⅰ ~組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例~
事例Ⅰは「組織(人事を含む)を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」です。
事例Ⅰの設問の王道的な流れは以下です。
- 環境分析:事例企業のSWOT分析をずばり問われることもある一方、少々婉曲的で回りくどい形で強みや弱みを聞かれたりすることも多いです。
- 過去の考察:過去に施策~~を実行したもののうまくいかなかった理由、××という状況に陥ってしまったのは何が足りなかったからなのかなど、これまでの流れの中から組織・人事的課題を浮き彫りにする問が中心となります。
- 今後の組織戦略:環境分析や今後の事業戦略を元に、どのような組織を醸成していくべきかが問われます。
- 今後の人事戦略:組織戦略を元に、従業員の能力やモラールをどのように高めていけばよいかが問われます。
対策として、組織構造、組織文化といった組織理論の基本を押さえた上で、人事施策によってどのように必要な人的資源を確保していけばよいかについて、助言できるようになるまで理解を深めておくことが重要でしょう。
特に、中小企業の事例として頻出テーマであるM&Aや事業承継については、起こり得る組織・人事的な問題とその対策方法を整理しておくことが重要かと思います。
また、近年では「両利きの経営」に代表されるような組織学習の観点についても重要な論点になりつつあるため、基本的な事柄について押さえておくことも重要です。
1. 組織論
概要
『組織論 補訂版』は、桑田耕太郎教授と田尾雅夫教授による深い洞察と幅広い知識を基にした書籍です。
全6章構成で、組織論の基礎から環境に組み込まれた組織、組織構造のデザイン、非営利組織に至るまで、組織論に関する内容を網羅しています。
本書籍は、組織理論を体系的に理解したい方、特に中小企業診断士2次試験の事例ⅠのINPUT教材として適していると考えます。
特長
- 日本型企業への洞察: 日本型企業の組織構造の問題点や改善策を詳細に解説し、現代の組織課題に対する具体的な洞察を提供します。
- 理論と実践の結びつき: 組織論のアカデミックな解説に合わせて実践的・具体的な事例がセットとなっているので、実務現場への応用をイメージしながら学ぶことができます。
- 詳細な構造分析: 組織の戦略的選択、組織文化、組織内プロセスなど、組織論の各側面について詳細な分析が行われています。
一方で、図表が少なく、専門的用語が多用されているため、初学者にとっては理解が難し感じられる部分もあるかもしれません。
学びのポイント
- 組織の定義や組織均衡についての理論の根底にある考え方とは何か?
- 組織文化の形成とその影響を深く考察することにより、どのように効果的な組織運営を行えば良いのか?
- 組織学習と変革に関する理論を活用することにより、組織の未来をどのように形作っていけば良いのか?
こんな人におススメ
『組織論 補訂版』は、特に中小企業診断士試験の受験生のみならず、組織・人事に関わっている方にもおすすめです。
特に日本型企業で見受けられやすい組織構造の問題点や改善策を詳細に解説し、実践的な事例を通じて、組織理論の本質を深く理解するための指針を提供します。
組織論の理解がキャリアアップに不可欠な方、理論と実践の結びつきを学びたい方には、この一冊が新たな視点と知見をもたらすことでしょう。
まとめ
組織論を深く理解し、実践的な知識を身につけたい方にとって、『組織論 補訂版』は必読の書籍です。
この一冊を通じて、組織の現在と未来に対する洞察を深め、より効果的な組織運営とキャリアの発展を図ることができるでしょう。
組織論の深い理解を目指して、この書籍を手に取ってみてはいかがでしょうか。
2. 事業承継の経営学
概要
この書籍では、事業承継を巡る論点を、豊富な企業事例と経営学の視点から平易に解説しています。
全体の構成としては、事業承継の基本概念から、後継者の育成、利害関係者との関係性構築に至るまで、幅広くカバー。特に、事業承継を契機にイノベーションを起こすことを根底に流れる主眼としています。
中小企業診断士試験対策としても最適ですが、その内容は中小企業経営者や関係者にとっても非常に参考になるものとなっています。従って、一般のビジネスマンにとっても事業承継の要諦を学ぶことができる機会となるでしょう。
著者の落合康裕氏は1973年兵庫県生まれ。大和証券に入社後、神戸大学大学院経営学研究科を修了しているそうです。専門は経営戦略論、経営管理論であり、特にファミリービジネス、事業承継に関する分野において顕著な研究成果を上げているとのことです。
特長
- 経営の現場からの知見: 日本のファミリービジネスや事業承継の現状について、具体的な事例を交えながら、縁故主義との違いや世界の視点からの評価を解説。経営者や事業継承者にとって、実際の課題解決のヒントになる内容です。
- 理論と実践の融合: 経営学の理論を事業承継の具体的なケーススタディに適用することで、理論的な知見と実務の架け橋を提供。事業承継を控える経営者や後継者にとって、実践的な指針となります。
- 多角的な視点: 事業承継が日本の産業活力に与える影響に触れ、ビジネススクールの学生や専門家にも有益な洞察を提供。事業承継の成功がもたらす可能性について考察し、新たな視点を提供します。
学びのポイント
- 事業承継の基本から後継者育成まで、事業承継を包括的にカバーするために、中小企業の経営者や後継者はどのような洞察を持っていれば良いのか?
- ファミリービジネスを承継する際、経営戦略と次世代組織の構築に立ちはだかるものとは何なのか?
- 事業承継における利害関係者との関係性構築について、具体的にどのような点に留意しておけば良いのか?
こんな人におススメ
- 中小企業の経営者や後継者で、実際に事業承継の複雑な問題に直面している方々には、本書籍は実践的なガイドとなるでしょう。
- 中小企業診断士試験の受験生にとっては、組織・人事事例の頻出テーマである事業承継について、理論と実践の間のギャップを埋めるための貴重な資料となるはずです。
- 多角的な視点と具体的なケーススタディが解説されているため、一般のビジネスパーソンにとっても事業承継に関する理解が深まるでしょう。
まとめ
事業承継は、中小企業の存続と成長にとって不可欠なプロセスです。
この複雑で重要なテーマについて、深く理解し、実践的な知識を身につけることは、あなたのキャリアにおいて大きな価値をもたらすでしょう。
「事業承継の経営学」は、そのための最適な一冊です。あなたのビジネスライブラリに加えてみてはいかがでしょうか?
3. 知識創造企業
概要
『知識創造企業』は、野中郁次郎、竹内弘高による経営学の名著です。
日本企業のイノベーションと「知識」の重要性を説くこの書籍は、近代の経営学研究に大きな影響を与えていると言われています。
内容は、組織における知識、知識と経営、組織的知識創造の理論、知識創造の実例、知識創造のためのマネジメントプロセス等のトピックを中心に、組織学習について理論的かつ詳細な解説がなされています。
特長
- 組織学習の理解: 中小企業診断士試験で頻出の組織学習の論点について、日本の第一人者が解説。
- 理論と実践の統合: 形式知と暗黙知のモデル、組織内での学習プロセスの理論的な理解と実際の事例研究。
- 批判的思考の促進: 本書はただの理論書ではなく、経済、哲学、歴史など多角的な視点から経営学を探求。
- 深い洞察と学び: 組織的知識創造の能力を深く理解し、それを製品やサービスに具体化する方法を学べます。
ただし留意点として、本書籍は前提とされる内容についての説明がそれほど丁寧とは言えないことが挙げられます。
そのため、全体を通して読み解くために著者の過去の著作などから足りない知識を補充することが求められる可能性がある点には注意が必要です。
学びのポイント
- なぜ、組織における知識創造が求められるのか?
- 知識創造のためのマネジメントプロセスはどのように運用されるべきか?
- 組織の形式知と暗黙知を統合するとは具体的にどういうことか?
こんな人におススメ
『知識創造企業』は、組織学習や経営理論に興味のある方、特に中小企業診断士試験の事例1対策を目指す方には必読です。
この書籍は、組織内での知識創造プロセスについて深く学べるだけでなく、マネジメントにおいてどのようなアプローチが有効かを教えてくれます。
理論と実践の両面から、組織学習の重要な側面を理解するための鍵となるでしょう。
まとめ
『知識創造企業』は、組織学習や経営の分野で深い知見を得たい方にとって、重要な一冊です。
特に中小企業診断士試験の準備中の方は、この書籍が提供する理論的枠組みと実例から、多くの洞察を得ることができるはずです。
あなたの組織やキャリアにおける知識創造のプロセスを深め、新たな視点を開くために、ぜひこの書籍を手に取ってみてはいかがでしょうか。
②事例Ⅱ ~マーケティング・流通を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例~
事例Ⅱは「マーケティング・流通を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」です。
事例Ⅱの設問の王道的な流れは以下です。
- 環境分析:事例Ⅱの環境分析については、シンプルにSWOT分析や3C分析が問われることが多いです。もし直接的に聞かれなかったとしても、後続の設問のために整理しておくことがほぼ必須と言えます。
- STP分析:環境分析をもとに、ターゲットとすべき顧客層やポジショニング戦略が問われます。特に、事例企業が持つ経営資源をどのように活用していくかが大事な視点になります。
- 4P戦略①:STPが定まった中で、具体的な4P戦略を落とし込んでいく設問が出題されます。4Pのうち価格戦略は問われる頻度は少ない傾向にあり、残りの製品、チャネル、プロモーションのいずれかがテーマになることが多いです。
- 4P戦略②:4P戦略①と別の論点でもう一問出題されるようなイメージです。特に、事例企業の今後の事業戦略とほぼ同義と言えるような、全体戦略に近い形で問われることが定番となります。
マーケティング理論には様々な理論やフレームワークが存在しますが、当然ではあるもののこれらを単純にあてはめるだけではうまくいくことは少ないです。
理論やフレームワークの原理の部分を理解した上で、中小企業ならではの戦略を前面に出し、独自サービスを展開していくような道筋を意識することが肝要となってくることでしょう。
1. 新マーケティング原論
概要
「新マーケティング原論」は、著者津田久資氏によるマーケティングの本質を掘り下げる一冊です。
著者はMBA取得後、博報堂やボストンコンサルティンググループでの豊富な経験を持っているそうです。
本書は、マーケティングの「定義」「目標」「戦場」「戦略」「道具」を詳細に解説し、理論と実践のギャップを埋めることに重点を置いています。
特に中小企業診断士試験対策として、理論の本質を深く理解したい方には有用と言えるでしょう。
特長
- 理論の根底を掘り下げる: マーケティング理論のフレームワークの背後にある理由とその有効性について、論理的に解き明かします。これは、中小企業診断士試験で求められる深い理解に直結します。
- 実践的な応用に焦点: 津田氏の経験に基づき、理論を現実のビジネスシーンにどう応用するかについて具体的な示唆を提供しています。特に「戦略」や「道具」の章では、実践に役立つ洞察が満載です。
- 参考になる実例と分析: 実際のビジネス事例を取り上げ、成功と失敗の要因を深く分析。これにより、読者は理論を具体的なビジネス状況に応用する方法を学べます。
ただし、本書は理論の深堀が前面に押し出された構成となっているため、理論的な内容が冗長に感じられるかもしれません。
特に、実践的な例を交えながら理解を深めたい場合は、別の書籍で補完する必要が出てきそうです。
学びのポイント
- マーケティング理論は私たちのビジネスにどのような影響を与えているのか?
- マーケティング理論は、なぜ具体的な経営戦略に適用されているのか?
- マーケティング理論の理論的背景を知ることで、どのような誤謬を防ぐことができるのか?
こんな人におススメ
- マーケティング理論について、手法だけでなく理論的背景を含めた深い理解を求める中小企業診断士試験受験者。
- 実践的なビジネス戦略の構築にマーケティングの知識を活かしたい経営者やマーケター。
- 理論と実践のギャップを埋め、具体的な戦略立案に役立てたいビジネスパーソン。
まとめ
「新マーケティング原論」は、ただの理論書ではなく、理論と実践の橋渡しをするための一冊です。
この本を読むことで、マーケティングの理論を深く理解し、実際のビジネスシーンでどのように活かせるかの洞察を得ることができます。
理屈からしっかり理解しないと気が済まないタイプの人にとっては、マーケティング論を学んだ時に感じたもやもやが解消されるに違いありません。
2. 小が大を超えるマーケティングの法則
概要
『小が大を超えるマーケティングの法則』は、岩崎邦彦教授による中小企業向けのマーケティングガイドです。
本書は、変化する市場において、小規模ながらどのように強みを生かすかを具体的に示します。
目次は、マーケティング的発想から「ほんもの力」「きずな力」「コミュニケーション力」まで多岐にわたります。
中小企業診断士試験対策としても重要な一冊です。
特長
- 中小企業の強みを活かす: 小規模ながらも市場で成功するための具体的な戦略が提示されています。
- マーケティング理論の実践: 実際の市場データと統計を用いて、理論を現実のビジネスシーンに応用する方法を解説。
- 多面的な視点: 商品の展示から顧客との関係構築まで、多角的な視点でアプローチを提案。
ただしタイトルの通り、本書籍は大企業とは異なる中小企業独自の視点から書かれているため、大企業向けの戦略を求める読者には不向きかもしれません。
学びのポイント
- 小規模企業が大企業に対抗するための戦略は何か?
- 中小企業が顧客との強固な関係を築くための具体的な方法とは何か?
- インターネットを活用したマーケティングで重要なのはどういったことか?
こんな人におススメ
この書籍は、特に中小企業経営者や中小企業診断士試験の受験者におすすめです。
小規模ながらも市場で成功するための具体的な戦略や、理論を現実のビジネスシーンに応用する方法が詳しく解説されています。
特に、「ほんもの力」「きずな力」「コミュニケーション力」の重要性を理解し、それをビジネスに活かしたい方には、非常に有益な内容が含まれています。
まとめ
『小が大を超えるマーケティングの法則』は、中小企業のマーケティング戦略を具体的かつ実践的に説明しています。
この書籍は、中小企業が直面する課題に対する深い理解と実践的な解決策を提供します。
中小企業の経営者や診断士試験の受験者が、現代のマーケティングの流れをつかむための必読書です。
今すぐ手に入れて、あなたのビジネスを次のレベルへと導きましょう。
3. サービス・マーケティング
概要
『サービス・マーケティング[第2版]』の著者、近藤隆雄氏はサービスマーケティングの専門家です。
本書では、サービスをプロダクトとしてどのように捉え、品質をどのように測定し、マーケティングに活用するかについて、深い知見を提供します。
全体の構成として、サービスの特性から始まり、サービスシステムの運営や革新に至るまで幅広いトピックがカバーされています。
これらは、中小企業診断士試験の受験者やビジネスパーソンにとって、非常に有益な情報と言えるでしょう。
特長
- サービス理解の深化: 本書は、サービスと物品の違い、サービス商品の分類、サービス品質の測定など、サービス業に特化した知識を提供します。これにより、サービス業界で働く方々や、サービスを改善したいビジネスパーソンにとって大きな助けとなるでしょう。
- 実践的なアプローチ: サービスマーケティングの理論だけでなく、具体的な事例を通してサービスの質をどのように測定し、改善するかについての実践的なアドバイスも提供します。
- 中小企業診断士試験対策: 特に、中小企業診断士試験の対策としても役立ちます。試験で問われるサービス関連の理論や事例が豊富に扱われており、試験対策に適しています。
サービス業界に携わる皆さん、また、サービス品質の向上を目指すビジネスパーソンにとって、この書籍はどのような新たな洞察を与えてくれるでしょうか?
ビジネスの世界においてサービス品質の重要性は高まる一方です。そうした中で、この書籍が提供する知識や洞察は、皆さんの業務やキャリアにどのような影響を与える可能性があるのでしょうか?
学びのポイント
- サービスと物品の違いとは何か?
- サービス品質をどのように測定すればよいか?
- サービスマーケティングミックスとは、具体的にどういうことなのか?
こんな人におススメ
サービス・マーケティングに関する基本から応用までを学びたい方、特に中小企業診断士試験の受験生やサービス業に携わるビジネスパーソンには最適です。
この書籍は、サービス業における品質管理やマーケティング戦略について、実践的かつ学術的な視点から深く掘り下げています。
サービス業をより高度に理解し、自社のサービス品質を向上させたい方には、特に有益な内容が満載です。
まとめ
『サービス・マーケティング[第2版]』は、サービス業に特化した深い知見を提供し、サービス品質の向上や効果的なマーケティング戦略の構築に役立ちます。
特に中小企業診断士試験の受験生やサービス業に携わるビジネスパーソンには必読の書籍となることでしょう。
サービス業界のマーケティング手法について、この書籍が新たな洞察を提供することを確信しています。
③事例Ⅲ ~生産・技術を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例~
事例Ⅲは「生産・技術を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例」です。
事例Ⅱの設問の王道的な流れは以下です。
- 環境分析:事例Ⅲの環境分析についても、基本的にはSWOT分析が求められるのは変わりありません。事例Ⅲでは改善すべき点が明白になっているケースも多く、その場合はもう少し踏み込んで、現状の生産現場で悪い点を挙げよ、のようにテーマがいきなり絞られていることもあります。
- 生産計画:事例Ⅲのテーマである生産については、生産の「計画」と「統制」の観点で診断・助言を行っていくのが定石となっています。
「計画」の観点とは、ざっくり言えば「作業標準として計画されている手順・工数などがそもそもイケてない(ムリムラムダがある)」ということです。 - 生産統制:もう一方の「統制」の観点とは、あるべきとして計画が正しく実行されるようにコントロールされていないということです。
例えば作業者の評価指標が生産計画と乖離したものになっていたり、生産現場においてあるべき姿から逸れた状態が常態化していたりなど、何らかの理由で計画通りになっておらず、かつそれが放置された状態になっている事例が出題されます。 - 投資意思決定:最後の設問として多く出題されるのが意思決定関係の設問です。中小企業にとって設備投資というのは非常に大きな意思決定となるため、今後の中長期的な事業戦略等とも整合を取った上で慎重に意思決定を行う必要があります。事例企業の全体的な方向性が問われ、事例Ⅲを締めくくるクライマックス的な設問となります。
設問の性質上、表面上ではなく本質的な課題を見抜く能力が求められますので、日頃の演習から構造的な理解を意識しておくと良いと思います。
1. 新人IErと学ぶ 実践IEの強化書
概要
『新人IErと学ぶ 実践 IEの強化書』は、日本インダストリアル・エンジニアリング協会によって編纂された一冊です。
2021年3月に出版されたこの書籍は、208ページにわたりインダストリアル・エンジニアリング(IE)の基礎から応用までを網羅しています。
対話形式で丁寧に内容が展開されていくため、新人だけでなく、IEを指導する立場にある人々にとっても参考になり得る構成となっています。
この本は、中小企業診断士の1次試験で理論を学び、2次試験の事例に対してどのように適用していけばよいかの橋渡しの役目として役立ちそうです。
特長
- 現場感覚の提供: 新人と指導者の対話を通じて、登場人物と一緒の立場になってIEの実践的学習を追体験できる構成になっています。そのため、実際の現場を目の前にしているかのような体験を提供します。
- 知識の習得: 新人IErに必要な知識が前半で対話形式で解説され、後半で分析ツールや考え方が詳述されています。こうした工夫によって、IEの専門書とは異なり、読むことで自然にIEの知識が習得できます。
- 実践的観点: 日本IE協会による編集で、IEの全体像を体系的かつわかりやすく伝えられています。そのため、現場感覚を学ぶための教科書としての役割を果たします。
学びのポイント
- インダストリアル・エンジニアリングは、実際の現場でどのように使われるのか?
- IEを活用して、どのようにして現場の「ムダ」を見つければよいのか?
- IEの体系的な分析手法は、どのように活用すれば成果につなげることができるのか?
こんな人におススメ
この書籍は、IEの基本を学習したものの、具体的な事例に対してどのように実践すればよいのかを学びたい中小企業診断士受験者に最適です。
もちろん、試験対策としてだけでなく、新人IErで実践的な現場知識と理論を同時に習得したい方や、現場指導者として新人に教えるための参考書としても有効です。
中小企業診断士試験の事例Ⅲ 生産・技術管理の手法としてIEは頻出であり、欠かすことのできないテーマと言えるため、過去問演習に取り組む前に一読しておくことは有効かと思われます。
まとめ
『新人IErと学ぶ 実践 IEの強化書』は、IEを学び、実践するための実用的な指南書です。
現場感覚を持ちながら理論を学びたい方や、新人を指導する立場にある方にとって、この書籍は貴重なリソースとなるでしょう。
実際の現場でのIEの実践に興味を持つ方は、この本を通して新たな視点を得ることができます。
ぜひこの機会に『新人IErと学ぶ 実践 IEの強化書』を手に取ってみてはいかがでしょうか。
2. なぜなぜ分析 実践編
概要
小倉仁志著『なぜなぜ分析 実践編』は、中小企業診断士試験を控えた方々や、製造現場での品質改善に取り組むプロフェッショナルにとって、非常に有益な一冊です。
本書は、エラー原因の根本解析に焦点を当て、表面的な解決策ではなく、根本的な解決策を導き出すための具体的な方法論を提供しています。
また、「ロジックツリー」の活用法にも深く触れており、複雑な問題を体系的に解決するための実践的なスキルを身につけることができます。
特長
- 課題解決のスキルアップ: 中小企業診断士としての専門性を高めるために必要な「なぜなぜ分析」の技術を、具体的な製造現場の事例を通して理解できます。
- 実践的なロジックツリーの応用: 課題解決に欠かせないロジックツリーの具体的な使用方法を学び、現場での問題解決能力を高めることができます。
- 試験対策としての効果: 中小企業診断士試験の「事例3」対策としても有効であり、試験で求められる思考法と実践的なスキルの両方を養うことが可能です。
本書は、表面上の解決策にとどまらず、問題の本質を見極める力を養うための実践的な一冊です。
中小企業診断士試験に向けて、また現場での品質管理や生産管理に携わるプロフェッショナルの方々にとって、必読の書籍と言えるでしょう。
さて、あなたはこの本からどのような新たな知見を得ることができるでしょうか?
学びのポイント
- 問題の根本原因を見つけ出す洞察力は、どのように鍛えていけばよいのか?
- 複雑な問題を構造的に整理するためにはどのような手順で進めればよいのか?
- 「なぜ」の探索を意識することで、なぜ情報処理能力が向上できるのか?
こんな人におススメ
中小企業診断士試験の対策を探している方々にとっては、この書籍は事例問題が求める能力の根底となる分析思考を意識できるようになることでしょう。
特に、現場の問題解決に対する道筋について、頭の中で勝手に探索してしまうくらいに、日頃から「なぜなぜ分析」で深堀を行うクセをつけておくことが重要です。
また、ロジカルシンキングや問題解析スキルを高めたいビジネスパーソンにとっても、この書籍は実践的な知識を提供することでしょう。
まとめ
『なぜなぜ分析 実践編』は、中小企業診断士試験の対策にも、実際のビジネスシーンでの問題解決にも役立つ一冊です。
問題の本質を見極め、効果的な解決策を導き出すための洞察力とスキルを身につけたい方々に、ぜひおすすめします。
3. 生産現場構築のための生産管理と品質管理
概要
『生産現場構築のための生産管理と品質管理』は、木内正光氏による中小企業の生産現場改善に特化した実践的な指南書です。
城西大学経営学部の准教授である木内氏は、豊富な工学知識と実務経験を融合させ、中小企業が直面する生産管理の課題に対する明確な解決策を提供しています。
本書は、生産現場の管理、生産性、品質、生産管理との接点、生産管理の機能、生産現場の設計など、重要なトピックを網羅しています。
中小企業の生産現場をデータと記号で分析し、具体的な改善策を示しています。
特長
- 生産効率の向上: 生産効率を高めるための具体的な方法論を提供し、中小企業の生産管理者が直面する実務問題に対する実践的なソリューションを提示します。
- 品質管理の強化: 品質管理の基本から応用までを詳細に説明し、品質の維持と向上のための実務的なアプローチを提供します。
- 生産管理の体系化: 生産管理の基本機能から生産計画、統制、MRPシステムに至るまで、生産管理の体系を理解するための包括的なガイドを提供します。
実務者はもちろん、中小企業診断士試験の受験生にとっても、この書籍は生産現場の理解を深め、実践的なスキルを身につけるための重要なリソースです。
学びのポイント
- QCDは既存のシステムやプロセスに対し、具体的にどのような影響を与えていくのか?
- 実際の現場において品質管理の理論を適用する際に起こり得る課題は何か?
- 生産管理を運用するために、どのようなスキルや知識が必要になるか?
こんな人におススメ
『生産現場構築のための生産管理と品質管理』は、中小企業の生産現場における効率化と品質向上を目指す方に特におススメです。
特に中小企業診断士試験の事例3対策を行っている受験生にとって、この書籍は1次試験の知識を強化すると共に、実践への生かし方などについてイメージを固めることが可能となるでしょう。
生産効率を向上させる方法、品質管理の具体的なアプローチ、生産管理の体系的な理解を求める方には、この書籍が明確な指針を提供してくれることでしょう。
まとめ
中小企業の生産現場を効率的かつ品質重視で運営したいと考える方々にとって、『生産現場構築のための生産管理と品質管理』は理論と実践が融合した貴重なガイドブックです。
この書籍は、生産管理の基本から応用までを網羅し、中小企業の生産現場における課題に対する具体的な解決策を提供しています。
生産効率の向上、品質管理の強化、生産管理の体系化に関心がある方は、この書籍を手に取ってみてはいかがでしょうか。










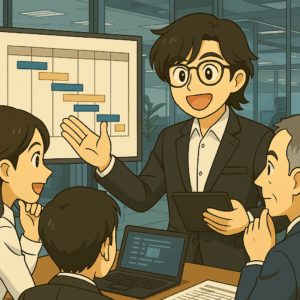
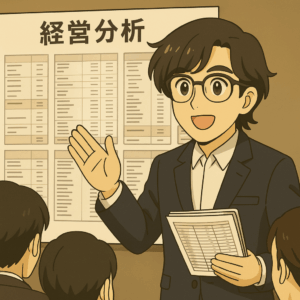


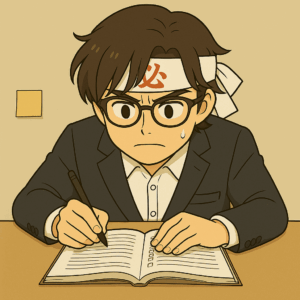
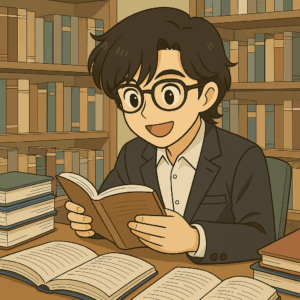
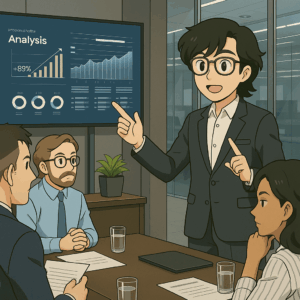
コメント