本記事では中小企業診断士2次試験の事例Ⅳにフォーカスし、独学で立ち向かうのに役立つと思われる書籍(参考書含む)9選を紹介します。
事例Ⅳの試験時間は80分で、およそ3つから4つの大問から構成されています。
メインテーマは財務やファイナンスの分野であり、具体的な計算過程を記述する点が他の事例問題と大きく異なります。
出題範囲としては例年ほとんど同じような形式となっており、財務諸表から経営分析を行い、その内容に元にCVP分析や設備投資分析などを行っていくのが標準的な流れとなります。
試験の特徴としては、とにかく試験時間の制約が厳しい点があると思います。
すなわち、論理的思考能力というよりも、情報処理の能力が求められている試験と言えます。
また、事例企業の設定に即して実践的な内容が問われるため、1次試験で学んだ理論面の知識だけでは太刀打ちできないほどに大きなギャップがあることが最初に留意すべき点と思われます。
そのため本記事では主に、独学で事例Ⅳの問題演習に入るためのステップとして
①基礎固め
②演習
③副読本
の3つのテーマについて書籍を紹介していきます。参考になれば幸いです。
なお、中小企業診断士2次試験に立ち向かうための基礎力を養うのにおススメの書籍については以下でまとめていますので、併せて参照いただけると幸いです。
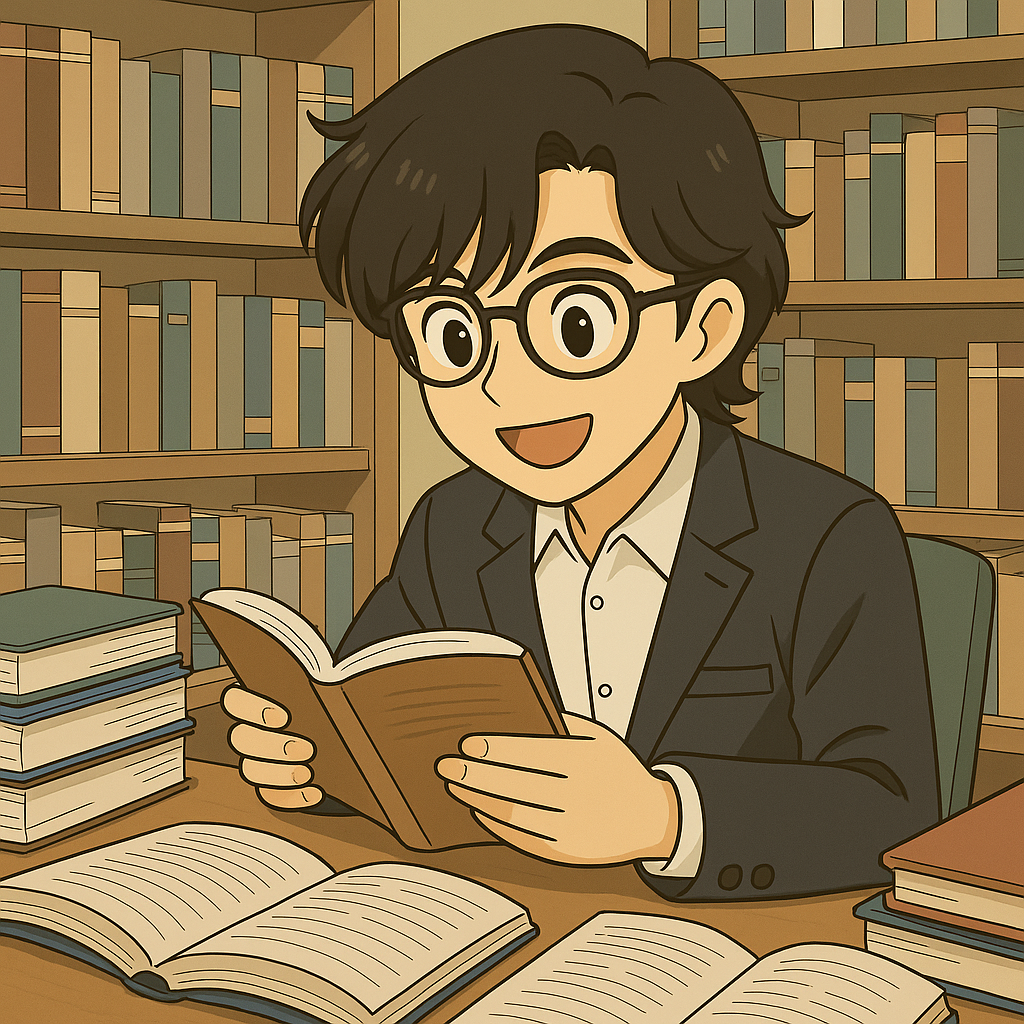
また、演習段階に入る際に有用な書籍は以下にまとめています。合わせて参照いただけると幸いです。
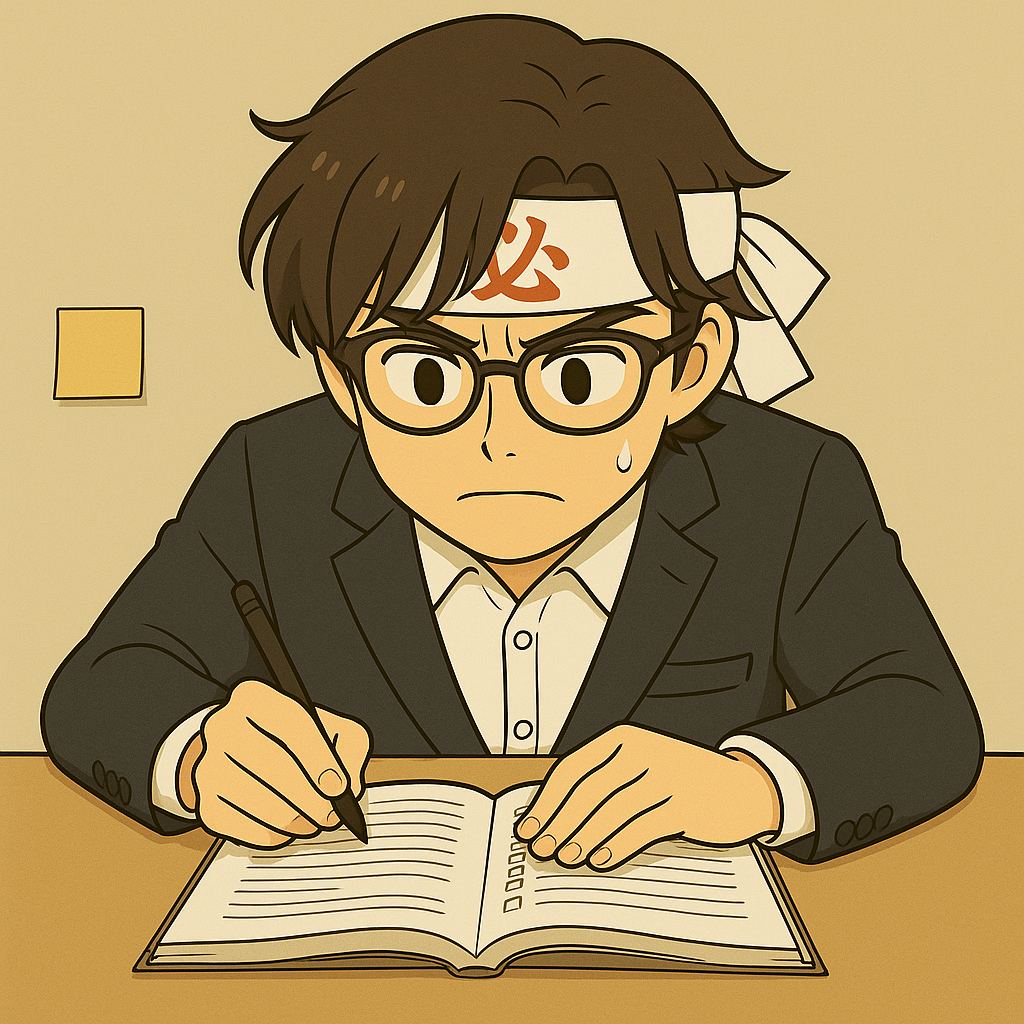
①基礎固め
すでに述べた通り、事例Ⅳの内容は1次試験で問われるレベルから大きく難易度が上がっています。
そのため、いきなり演習に入ろうとしても全く手が付けられず、望ましい効果は得られない可能性が高いです。
そこで、まずは「基礎固め」として財務諸表の分析の全体像をつかむための書籍を読んでイメージを掴んでおくのが良い戦略になるかと思います。
また、管理会計分野の理論について、1次試験の時以上に各分析手法の意味などを深く理解しておく必要があるため、そうした分野の解説書を読んでおくことが重要になるかと思います。
1. 財務3表一体理解法「管理会計」編
概要
中小企業診断士2次試験に挑む皆さんにとって、事例Ⅳの会計・財務問題は最も大きな壁のひとつです。
特に管理会計の分野は、知識を暗記するだけでは対応できず、「与件企業の状況を数値の裏側から読み解く力」が必要となります。
そこで紹介したいのが、國貞克則氏の『財務3表一体理解法「管理会計」編』です。
本書は、累計ベストセラーとなった「財務3表一体理解法」シリーズの最新編で、管理会計を切り口にした一冊です。
管理会計というと「原価計算」「予算管理」「投資評価」など多岐にわたり複雑ですが、著者はそれらを財務3表のつながりの中で解説し、読者が体系的に理解できるように構成しています。
原価計算では「利益がどこにあるかを明確にする」、予実管理では「予算をエネルギー動員の仕組みとして捉える」、キャッシュフロー管理では「利益と現金の違いを明確にする」といった形で、実務にも直結するテーマが扱われています。
診断士試験では、売上やコストの差異分析、限界利益の把握、投資採算性の評価といった知識が問われますが、それらを単なる公式の暗記ではなく「なぜ必要なのか」「どう活用するのか」という経営の現場感覚で捉えられる点が本書の強みです。図解や具体例も豊富で、数字が苦手な方にも学びやすい構成になっています。
学びのポイント
- 管理会計とは財務会計とどう違い、なぜ経営分析をする上で重要なのか?
- 限界利益(貢献利益)は企業の意思決定においてどんな意味を持つのか?
- 利益は「意見」、現金は「事実」とはどういう意味で、なぜ重要なのか?
- キャッシュフローを見ることで、経営の安全性をどう判断できるのか?
- 事業再生の考え方を管理会計の視点からどう整理できるのか?
こんな人におススメ
「管理会計の用語は暗記したけれど、実際の事例でどう生かせばよいのか分からない」――そんな悩みを持つ受験生には、本書が大きな助けになるでしょう。
事例Ⅳでは限界利益、損益分岐点、原価差異分析、投資評価といった論点が頻出しますが、本書はそれらを経営管理の道具として一体的に解説しています。
そのため、「計算問題」から「経営戦略とのつながり」まで、知識を橋渡しする役割を果たします。特に有益なのは「予実管理」の章です。
試験でも問われる差異分析の考え方を「どのように意思決定やフィードバックに使うのか」という文脈で理解できるため、単なる計算練習にとどまらず与件文読解の精度を高められます。
また、キャッシュフローと利益の違いを押さえることで、数字の裏にある経営実態を把握でき、解答の説得力を増すことにもつながります。
一方で、DCF法やIRRといった投資評価の部分はやや高度で、初学者にはとっつきにくい箇所もあります。また、演習問題集ではなく理論解説が中心のため、計算練習を積みたい人は別の問題集を併用する必要があります。
そのため、数字を「戦略的に読む力」を伸ばしたい人には強くおすすめできますが、「とにかく計算ドリルを回したい」という人には物足りなく感じるかもしれません。
まとめ
中小企業診断士2次試験において、管理会計は単なる数字合わせではなく「経営判断の根拠」として問われます。
『財務3表一体理解法「管理会計」編』は、その本質を体系的かつ平易に学べる一冊です。原価計算や予実管理を財務3表にリンクさせて理解できるため、断片的に覚えていた知識が一本の筋としてつながり、与件文の分析に活かせる力を養えます。
もちろん、試験対策としては別途の計算問題集で演習を積むことが必要ですが、「なぜこの計算をするのか」「経営にとってどのような意味があるのか」を理解しているか否かで、解答の説得力や再現性は大きく変わります。
本書はその理解を確実に後押ししてくれるでしょう。
診断士試験に向けて、あなたは「数字を解く力」だけでなく「数字を語る力」を身につけたいですか?その答えが「はい」なら、この本がその第一歩になるはずです。
2. 会計指標の比較図鑑
概要
中小企業診断士2次試験を控える皆さんにとって、事例Ⅳの財務分析や指標の解釈は避けて通れないテーマです。
しかし、「ROEやROAの計算はできるけれど、与件文とのつながりがうまく掴めない」という悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
そこで紹介したいのが、矢部謙介氏の『会計指標の比較図鑑 見るだけでKPIの構造から使い方までわかる』です。
この本の最大の特徴は、40社の実在企業を取り上げて、決算書を図解とともに比較できる点にあります。
貸借対照表や損益計算書を「比例縮尺図」や「ウォーターフォールチャート」で可視化し、数式だけでは見落としがちな指標の背景や意味を直観的に理解できるよう工夫されています。
さらに、同業他社との比較や年度ごとの推移を追うことで、戦略やビジネスモデルの違いが数字にどう反映されるのかを学べる点がポイントです。
診断士試験の与件文では、「この企業はなぜこのような収益性なのか」「なぜ効率性が低いのか」といった分析が必須になります。本書を通じて、単なる計算練習にとどまらず、数値と経営戦略を結びつける視点を鍛えられることは、まさに事例ⅡやⅢの思考とも直結するでしょう。
学びのポイント
- 貸借対照表を図解すると企業戦略の違いがどのように見えてくるのか?
- 売上高営業利益率はなぜ業種によって大きく異なるのか?
- 流動比率や自己資本比率はなぜ安全性の重要指標とされるのか?
- 資産回転率は企業の効率性をどのように評価するのか?
こんな人におススメ
もしあなたが「財務指標の意味は知っているつもりだが、与件文にどう落とし込めばよいのか分からない」と感じているなら、この本は非常に役立ちます。
中小企業診断士2次試験では、単純に利益率や回転率を暗記しているだけでは対応できません。なぜその数値が生まれたのか、企業の戦略やビジネスモデルのどの要素が影響しているのかを読み解く力が問われます。
本書はまさにその橋渡し役です。製造業からサービス業まで、異なる業界の実際の企業を比較することで、「同じ収益性指標でも背景は大きく異なる」という理解が自然に身につきます。
また、図解により一目で構造が把握できるため、学習効率が高いのもポイント。与件文の読み込みと数値分析を結びつける訓練を、実際の企業データを通じて積むことができます。
ただし注意点としては、図解や比較に重点を置いている分、個別の計算プロセスや理論の掘り下げはやや薄めです。
そのため「事例Ⅳの計算練習を徹底的にやりたい」という方には物足りないかもしれません。一方で、数値を戦略の文脈に落とし込みたい受験生には強く推奨できる一冊です。
まとめ
中小企業診断士2次試験において、数値の計算力はもちろん大切ですが、最終的に求められるのは「数値を経営戦略と結びつけて解釈する力」です。
『会計指標の比較図鑑』は、40社の実在企業を比較することで、その力を養う最適な教材となります。図解を通じて会計指標の構造を視覚的に理解でき、与件文の背景にあるビジネスモデルを読み解く視点を自然に鍛えられるでしょう。
財務指標の暗記に頼らず、戦略的に数値を読み解く思考回路を作ることは、事例Ⅳだけでなく、事例ⅡやⅢの解答精度を高めることにもつながります。受験勉強の中で「数字と文章をどうつなげるか」に悩んでいる方にとって、本書は強力な助けとなるはずです。
計算練習そのものを重点的に行いたい場合には、別の問題集との併用が必要になるでしょう。それでも、「指標を読む力」を養いたい診断士受験生にとっては、読む価値の高い一冊です。
3. 管理会計本格入門
概要
「管理会計本格入門」は、駒井伸俊氏によって書かれた書籍で、中小企業診断士試験の受験者や財務諸表分析に関心がある方々に最適です。
駒井氏は株式会社イーバリュージャパンの代表取締役および税理士事務所の所長であり、豊富な経験と専門知識を持ち合わせています。
この書籍では、管理会計の基礎から戦術的、戦略的意思決定に至るまで幅広いトピックを網羅しています。
その内容は、短期的な意思決定、CVP分析、原価分解などの戦術的な視点から、資本コストやバランスト・スコアカードを含む戦略的意思決定までを包括。
現場からマネジメントへの役割変更を目指す方や、ビジネスリーダー、コンサルタントを目指す方にも役立つ内容です。
特長
- 実践的視点: 本書は、中小企業診断士試験の事例4対策に特化し、管理会計の実践的な視点を体系的に学べます。財務諸表分析における誤判を防ぐ方法を学びたい受験者には特にお勧めです。
- マネジメントへの移行: 財務諸表を見た経験はあるが、マネジメントへの役割変更や意思決定に自信がない方にとって、この書籍は必須のガイドです。実践的な管理会計のアプローチを通じて、より確かな意思決定能力を身に付けることができます。
- 計数的スキルの向上: 将来のビジネスリーダーやコンサルタントを目指す方には、計数的スキルの向上に役立ちます。特に、戦略的意思決定や原価管理のための管理会計は、実務での応用が期待できます。
この書籍は、管理会計についての理論と実践を深く理解したい方々にとって、貴重なリソースとなることでしょう。
ただし、財務諸表の基本的な知識がないと理解が難しい部分もあるため、深く理解のためには基本知識の補充が必要となりそうです。
学びのポイント
- 管理会計は、具体的にビジネス上のどういった場面で重要なのか?
- CVP分析や原価分解は、日々のビジネス決定を管理会計の視点から見直したい方にとって、どのように役立つか?
- 資本コストやバランスト・スコアカードは、ビジネス戦略を計数的に分析し、より効果的な決定を下すためにどのように活用できるか?
こんな人におススメ
「管理会計本格入門」は、特に次のような方々におススメです:
- 中小企業診断士試験の受験者や、財務諸表分析に関心がある方々。特に、試験対策や実務における誤判を防ぐための具体的な知識を獲得したい人。
- 現場からマネジメントへの役割変更を目指す方々。特に、管理会計の視点から意思決定を行い、自信を持ってビジネスを進めたい人。
- ビジネスリーダーやコンサルタントを目指す方々。計数的スキルの向上により、社内の重要な役割に必要なスキルを獲得したい人。
まとめ
「管理会計本格入門」は、管理会計の理論と実践に深く関心を持つ方々にとって、非常に価値のある一冊です。
著者の駒井伸俊氏は、その豊富な経験と専門知識を通じて、読者に重要な洞察と実用的な知識を提供しています。
この書籍を通じて、より確かなビジネスの意思決定ができるようになることでしょう。
管理会計の知識を深めてビジネススキルを向上させたいと考えている方には、本書籍をぜひご一読いただければと思います。
②演習
基礎固めとしてINPUTがある程度完了したら、ひたすら手を動かして演習するフェーズに入ります。
ここに挙げている参考書は、いずれも中小企業診断士の独学合格者の間で評価が高く、安心して注力できます。
逆に、ここで挙げた以外の参考書というのがほとんど無いのが実状で、裏を返せばこれらの参考書の水準を自在に扱えるようになっていれば、大多数の受験者と同等のレベルに到達できることになります。
個人的なおススメとしては、これらの参考書の計算問題については、1周目は実際に手を動かして解き、2周目以降は頭の中で解法を大まかに組み立てて、方針だけ答え合わせをする使い方が良いと思います。
理論的な解説については一旦読み込んだ上で、「副読本」を手元に置きながら解説を補充していくスタイルが最もタイパが高いのではないかと思います。
1. 中小企業診断士 第2次試験 事例IVの解き方
概要
中小企業診断士第2次試験の中でも、事例IVは多くの受験生にとって最大の難関です。
特に、事例IVに苦手意識を抱える受験生にとっては「どこから手をつけてよいか分からない」「何度解いても同じミスを繰り返す」といった悩みが尽きません。
そうした課題に応えるのが『中小企業診断士 第2次試験 事例IVの解き方』です。
本書は、経営分析・CVP分析・キャッシュフロー計算書・意思決定会計・設備投資・企業価値といった出題分野を6テーマに整理し、それぞれについて「基礎問題」「応用問題」「本試験問題」の3ステップで演習できる構成になっています。
段階的に取り組むことで、基礎理解から応用力、そして本試験レベルでの実戦力へと着実にステップアップできる点が最大の魅力です。
さらに、TAC講師による解説は単なる答え合わせにとどまらず、「どの順序で考えるか」「どこに着目するか」といった答案作成に直結する思考法を示しており、自分の解法プロセスを確立するのに役立ちます。
過去に事例IVで悔しい思いをした方にとって、本書は弱点を克服し、再挑戦への自信を取り戻すための頼もしい相棒となるでしょう。
こんな人におススメ
事例IVにおいて失敗を経験した受験生の多くは、知識不足そのものよりも「答案作成力の欠如」に悩まされています。数字を使った分析や計算はできても、それを限られた時間内に論理的に答案に落とし込むのは容易ではありません。
本書『中小企業診断士 第2次試験 事例IVの解き方』は、まさにその課題を克服するための構成を備えています。各テーマを基礎・応用・本試験の3段階に分け、段階的に学習を進めることで、ただの「演習の繰り返し」ではなく、確実に答案力が積み重なる仕組みになっています。
さらに、解説は単なる正答の提示ではなく、講師の思考プロセスを追体験できる形式です。どのように与件文を読み取り、どの順序で計算や記述に落とし込むのかを具体的に示してくれるため、自分の答案作成法を磨くヒントになります。
過去に失敗した受験生にとって、この「答案プロセスの型」を身につけられることは何よりの収穫となるでしょう。
ただし注意点もあります。本書は演習量が豊富であるがゆえに、計画的に学習を進めなければ途中で消化不良に陥るリスクがあります。
独学の場合は特に「どの章をいつまでに終えるか」を明確に定め、学習スケジュールを守ることが前提条件です。
その点を理解できれば、事例IVの再挑戦を成功に導くための有力な武器となるでしょう。
学びのポイント
- 経営分析では、どの指標を選び、なぜその指標が重要となるのか?
- CVP分析を使うことで、利益計画や意思決定にどのようにつなげられるのか?
- キャッシュフロー計算書から、企業の資金繰りをどう読み解くべきか?
- 意思決定会計において、短期的判断と長期的視点をどうバランスさせるのか?
- 設備投資の経済性計算で、投資判断を下す基準は何を重視すべきか?
- 企業価値評価を試験問題にどう適用し、解答を組み立てればよいのか?
- 応用問題に挑む際、複雑な与件文をどう整理して答案に落とし込むのか?
- 本試験問題を解くとき、限られた時間で計算精度と答案完成度をどう両立させるのか?
まとめ
事例IVは、中小企業診断士第2次試験の中でも「最後の壁」と言われるほど、多くの受験生が苦手とする分野です。
特に過去に失敗した経験を持つ方にとっては、「再び同じ結果になるのでは」という不安がつきまとうものです。
しかし、課題の本質は財務知識そのものではなく、それを答案にまとめ上げる力の不足であるケースが大半です。『中小企業診断士 第2次試験 事例IVの解き方』は、この弱点に真正面から応える教材です。
基礎問題で理解を固め、応用問題で思考を広げ、本試験問題で実戦力を高める──この3ステップの演習構成は、答案作成力を段階的に鍛えるために極めて有効です。また、TAC講師が示す「解答プロセス」は、答案に至るまでの思考の型を明確にし、再現性のある解法を自分のものにする手助けとなります。
一方で、演習量が多いがゆえに独学で進める場合は学習計画が不可欠です。無計画に取り組むと途中で挫折し、せっかくの教材を活かしきれない恐れがあります。
したがって、本書は「過去に事例IVでつまずいたが、再挑戦を本気で成功させたい」と考える受験生にこそ最適な教材となるでしょう!
2. 事例IVの全知識&全ノウハウ
概要
『事例IVの全知識&全ノウハウ』は、岩間隆寿、霜田亮他によって監修された中小企業診断士2次試験の受験生向けの専門書です。
400ページにわたる本書籍は、受験生が限られた準備期間内で事例IVの対応力を合格レベルに高めることを目的としています。
内容は、平成18年度から最新年までの過去問をテーマ別に編集し、経営分析、損益分岐点分析(CVP)、その他意思決定会計など多岐にわたるテーマを網羅しています。
事例4を合格水準のレベルまで引き上げたい独学受験生にとっては有用な一冊となるでしょう。
特長
- テーマ別編集: 受験生が事例IVの過去問をテーマ別、難易度別に効率よく学習できるように編集されています。特に頻出のテーマから学べるのは大きな利点です。
- 計算問題への対策: 事例IVの計算問題に対する効率的な解法が学べます。計算問題が苦手な受験生にとって、この部分は非常に重要です。
- 実践的なノウハウ: 理論の解説はもちろんのこと、実際の試験で役立つノウハウも網羅。合格を目指す受験生にとって、この実践的な内容は大きな強みとなります。
念のため留意点として、本書籍は中小企業診断士試験の受験生を対象としています。
そのため、一般のビジネスパーソンや財務分析に興味がある方にとっては内容が特化しすぎている可能性があります。
こんな人におススメ
中小企業診断士試験の受験生の皆さん、事例IVの過去問に効率的にアプローチしたいですか?計算問題の解法をマスターしたいですか?それなら、この書籍があなたの強い味方になることでしょう。
事例IVの対策が苦手で、より効果的な学習方法を探している受験生に特におススメします。
まとめ
『事例IVの全知識&全ノウハウ』は、中小企業診断士試験の受験生にとって必携の書籍です。効率的な学習法、計算問題の攻略法、実践的な知識の習得と、必要なすべてがこの一冊に凝縮されています。
事例IVでの成功を目指す受験生は、ぜひこの書籍を手に取ってみてください。あなたの合格への一歩を、この書籍がしっかりとサポートします。
3. 事例Ⅳハイスコアマスター
概要
中小企業診断士2次試験の事例Ⅳは、多くの受験生にとって最大の関門です。財務・会計の知識をベースに、精緻な計算力と論理的な説明力が求められ、ケアレスミスひとつで大きな失点につながります。
そんな厳しい戦場で「80点超え」を現実的に目指すために作られたのが『事例Ⅳハイスコアマスター』です。
本書はステージ制を採用しており、基礎から応用へと段階的に力を積み上げられる構成になっています。
ステージ0で「学習法の基本」、ステージ1で「経営分析」、ステージ2で「CVP分析」、ステージ3で「設備投資」、ステージ4で「複合問題」と、診断士試験の出題傾向に沿った実践的なトレーニングを重ねていけるのが特長です。
各ステージは「サマリー(基礎解説)」→「バトル(問題演習)」→「解答・解説」の三段階で構成されており、理解から実践、定着へとスムーズに進める設計となっています。
総問題数は51問と十分なボリュームがあり、解答用紙(PDF)の特典ダウンロードも用意されているため、実際の試験環境を想定した練習が可能です。
単なる知識確認にとどまらず、ケアレスミス防止のコツや条件整理の仕方など、実戦での得点力を底上げする工夫が随所に盛り込まれています。まさに「合格レベルからさらに一歩踏み込んで高得点を狙う」ための一冊です。
学びのポイント
- 経営分析の主要指標をどのように組み合わせて評価すべきなのか?
- CVP分析で損益分岐点や安全余裕率をどう計算・解釈すべきなのか?
- 設備投資の採算性をNPVやIRRで評価する際の注意点は何か?
- 複合問題において複数の論点をどう整理して解答にまとめるのか?
- ケアレスミスを防ぐために答案構成で気を付けるべきことは何か?
- 制限時間の中で効率的に計算を進めるための工夫とは?
- 与件文から必要なデータを素早く拾い出すにはどうすればよいのか?
- 計算問題を正確に処理するためにどのように検算を行うのか?
- 80点超えを狙うための得点戦略はどのように立てればよいのか?
こんな人におススメ
「過去問を一通り解いたけれど、点数が安定しない」「経営分析やCVP分析は理解しているつもりなのに、本番で失点してしまう」――そんな悩みを抱える受験生にこそ、本書は有効です。
診断士試験では単に公式を知っているだけでは不十分で、限られた時間で正確に処理し、ミスなくまとめ上げる力が要求されます。本書の段階的な演習を通じて、思考の整理から答案作成までを一気通貫で訓練できる点が大きな魅力です。
また、近年の事例Ⅳでは「複合問題」の出題が増えており、複数の論点を組み合わせた応用力が試されています。
本書のステージ4はまさにその対策を目的としており、基礎力を土台にして複雑な問題を解き切る力を養うことができます。
さらに、実務経験豊富な著者陣の解説は具体的でわかりやすく、知識を暗記するだけでは得られない「本番で点を取るための勘所」をつかむことができるでしょう。
一方で、基礎知識の確認よりも「得点力の強化」に重きを置いているため、初学者が最初の教材として使うにはやや難度が高いかもしれません。
基本書で一通り学習を済ませた上で、本格的な過去問演習に入る前のさらなるレベルアップを目指す人にとって、必要十分かつ高タイパの問題集となり得るでしょう。
まとめ
事例Ⅳで安定して得点を積み上げられるかどうかは、合否を大きく左右します。
『事例Ⅳハイスコアマスター』は、単なる知識確認ではなく「本番で点を取る力」を鍛えることを目的とした実戦的な問題集です。ステージ制によって基礎から応用へと段階的に力をつけられ、さらに複合問題までカバーしている点は、近年の試験傾向に合致しています。
もちろん、基礎の習得を終えた中級者以上向けという点は注意が必要です。しかし、過去問をある程度解いて実力の伸び悩みを感じている方にとって、本書は飛躍のきっかけになるでしょう。
実際の試験を意識した演習を繰り返すことで、精度とスピードを兼ね備えた計算力を養うことができます。
あなたは、事例Ⅳで「合格点を取る」だけで満足しますか?それとも「80点を超えて余裕を持って合格を掴む」ことを目指しますか?その答えが後者なら、この一冊が強力な武器になるはずです。
③副読本
最後に「副読本」です。
すでに挙げたような参考書で演習を重ねると、様々な疑問が浮かんでくることが多いと思います。
しかし、独学ではなかなか聞ける人もいないし、Web検索したとしても突っ込んだところが分からないということがあるのではないかと思います。
そのため、専門的な分野について辞書的に調べられるような副読本を用意しておくと安心できます。
特に、私もそうですが、細かい部分の理屈が理解できずにずっと気になってしまう方は、手元に置いておくことを検討してみてもいいかもしれません。
1. 道具としてのファイナンス
概要
『道具としてのファイナンス』、著者は石野雄一氏。米国インディアナ大学ケリースクール・オブ・ビジネス(MBA課程)を修了し、企業投資の専門家として活躍しています。
この書籍は、ファイナンスの基礎から応用までを、実例を交えてわかりやすく解説。特に中小企業診断士試験の受験生や、事例4の過去問に挑む方に最適です。
数式を極力避け、Excelを用いた実践的なアプローチを採用。資金調達やプロジェクト選択など、ファイナンスの実務に直結する知識が身につきます。
特長
- 実践的な学習法: 数式を避け、Excelを使った実践的な方法でファイナンス理論を理解。これにより、理論が具体的な実務にどう生きるのかが明確に。
- 中小企業診断士試験対策: 事例4の過去問で出題されるファイナンス分野に特化。一通りの知識を効率的に確認し、試験への対策が可能。
ただし留意点として、本書籍は数式を使った解説があるため、数式が苦手な初学者には他の入門書と併用することをお勧めします。
学びのポイント
- 実務への直結: この書籍を読むことで、理論を現実のビジネスシーンにどう応用するかが学べます。具体的なExcelの使用例は、実際の業務にどう活かせるのでしょうか?
- 試験対策の強化: 中小企業診断士試験におけるファイナンス分野の理解が深まります。試験で求められる知識を、どのように身に付けることができるのでしょうか?
- 数式の理解: 数式を避けつつも、理論の理解を深めることができます。数式が苦手な方でも、どのようにしてファイナンス理論を理解することができるのでしょうか?
こんな人におススメ
- 中小企業診断士試験の受験生、特に事例4の過去問に挑む方。
- ファイナンスの基礎知識はあるが、より実践的な学びを求める方。
- 数式に不慣れな初学者でも、実例とともに学びたい方。
この書籍は、ファイナンスを実務に活かす方法を学ぶのに最適です。しかし、数式が苦手な方は、他の入門書と併用することをお勧めします。
まとめ
『増補改訂版 道具としてのファイナンス』は、ファイナンスの基礎から実践的な応用までをカバーする一冊です。
中小企業診断士試験の受験生や、実務でファイナンスの知識を活かしたい方には特にお勧めします。
数式に苦手意識がある方も、この書籍を通して理解を深めることができるでしょう。ファイナンスの理解を一歩進め、ビジネスの現場で活かす準備はできていますか?
2. 戦略思考で読み解く経営分析入門
概要
『戦略思考で読み解く経営分析入門』は、大津広一氏による財務分析の教科書です。
慶應義塾大学卒業後、米国公認会計士として活躍する著者が、12の重要財務指標をケーススタディを交えて解説。
この書籍は、事例4でよく出題される財務指標分析の深い理解を目指す中小企業診断士試験受験生に最適です。
財務諸表と会計指標へのアプローチ方法が明確に示されています。
特長
- 実践的理解: 会計指標の計算だけでなく、その背後にある経営戦略を理解することが可能。
- 具体的なケーススタディ: 具体的な企業の分析例を通じて、理論が実際のビジネスシーンでどのように応用されるかが学べます。
- 論理的な構成: 分厚い内容ですが、見やすく、理解しやすい構成。初学者から上級者まで幅広く役立ちます。
- 応用力の向上: 単なる知識の習得に留まらず、自身での分析力や説明力を高めることができます。
「財務指標をどう理解し、どう活用するか」、この一冊で、あなたの分析力は次のレベルへと進化するでしょう。
学びのポイント
- 財務諸表から読みとれる各指標は、どのように経営戦略と結びつくのか?
- 理論を実際のビジネスシーンに応用する際に意識し得おくべきこととは何か?
- 財務指標の背景にある経営の意図や戦略について、どのように読み解くことができるか?
こんな人におススメ
- 財務指標の計算方法を学びたい方
- 実際の企業事例を通して学びたい方
- 経営戦略と財務指標の関連性を深く理解したい方
この書籍は、単なる理論ではなく、実践的な知識を身につけたい方に最適です。
まとめ
『戦略思考で読み解く経営分析入門』は、単に財務指標を学ぶだけではなく、それを経営戦略に活かす方法を学べる貴重な一冊です。この書籍を読むことで、より実践的で深い分析スキルが身につくでしょう。
財務分析に新たな視点を求めている方には、間違いなくお勧めの一冊です。
3. 管理会計〔第七版〕
概要
中小企業診断士2次試験において、事例Ⅳの計算問題に加えて、与件文を踏まえた管理会計的な分析力が求められることはご存知の通りです。財務諸表分析や原価管理、意思決定会計など、幅広い知識が必要となります。
その総合力を鍛えるために紹介したいのが、櫻井通晴氏の『管理会計〔第七版〕』です。
本書は管理会計の定番教科書として位置づけられており、基礎的な原価計算から予算管理、損益分岐点分析、投資評価に至るまで、ほぼすべての主要論点を網羅しています。
さらに最新改訂版では、AIやIT投資、ガバナンスコードといった現代的テーマにも触れており、理論と実務をつなぐ視点が強化されています。
ページ数は約1000ページに迫る大著ですが、体系的に整理されているため、診断士試験の学習に必要な「利益管理」「原価管理」「意思決定会計」などを重点的に学べば、試験対応に直結します。
特に、直接原価計算・CVP分析・設備投資の意思決定・標準原価計算などは、過去問にも頻出の論点であり、理解の深まりが解答力の安定につながります。
学びのポイント
- 予算統制と差異分析は経営改善にどのように役立つのか?
- 損益分岐点分析を用いることで、経営戦略にどんな示唆が得られるのか?
- 直接原価計算と全部原価計算はどのように意思決定に影響するのか?
- 標準原価計算はコスト管理や業績評価にどう活用できるのか?
- ABC(活動基準原価計算)はなぜ現代の管理会計で注目されるのか?
- 設備投資の評価においてNPVやIRRはどのように活用されるのか?
- バランスト・スコアカードは戦略的マネジメントにどんな効果をもつのか?
- AIやIT投資は管理会計の実務にどのような変革をもたらしているのか?
こんな人におススメ
「過去問の解説で見た理論をもっと掘り下げて理解したい」「計算式は覚えているが、なぜその式を使うのかが腹落ちしていない」――こうした悩みを持つ受験生にこそ、本書は有用です。
診断士試験では、単なる計算力ではなく、経営戦略や与件の状況とリンクした解釈力が問われます。本書はまさにその橋渡しをしてくれる教材です。
例えば、第2部「利益管理」では予算統制や損益分岐点分析を体系的に学ぶことができ、与件文から差異要因を解釈する力が養えます。
また、第3部「原価管理」では標準原価計算やABC、品質コストなど、実務に即した内容が扱われており、解答の背景知識として役立ちます。
さらに、第4部「意思決定会計」は自製か購入か、投資採算性などの事例Ⅳ典型問題と直結しており、実践的な学習が可能です。
ただし、本書は学術的内容も含むため、初学者が「最初の一冊」として使うには分量も内容も重厚です。基礎を固めたうえで、理解を深めたい受験生に向いています。
試験直前期に全部を読み切るのは現実的ではありませんが、過去問で頻出する分野を重点的に拾い読みするだけでも、大きなアドバンテージになります。
まとめ
『管理会計〔第七版〕』は、中小企業診断士試験に必要な知識を網羅的に学べるだけでなく、実務とのつながりまで意識した内容を備えています。基礎理論に加え、予算管理・CVP分析・設備投資評価といった試験頻出分野をしっかり理解できるため、事例Ⅳの安定した得点力につながるでしょう。
一方で、内容が膨大なため、すべてを読み切る必要はありません。自分の弱点分野を補強する目的で必要な章を選んで学習するのが効果的です。
その際、必ず過去問演習とセットで使い、「理論の理解」から「実践での応用」へとつなげることが重要です。
あなたは、単なる計算力にとどまらず、数字を経営の文脈で語れる力を試験に持ち込みたいですか?もしもそうであれば、この一冊は確実にその助けになるはずです。










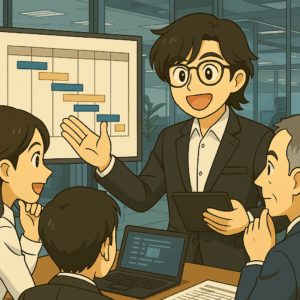
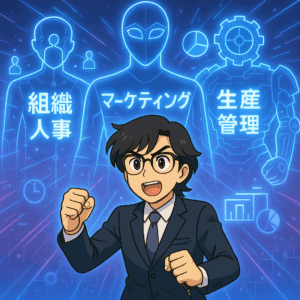


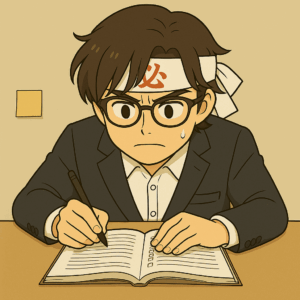
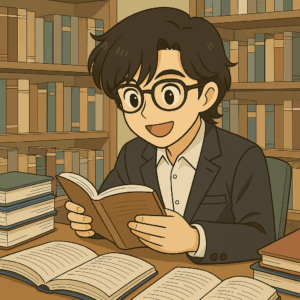
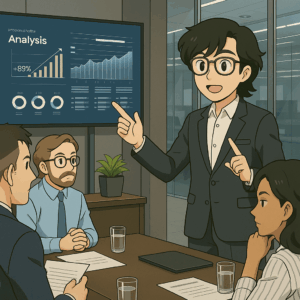
コメント