本記事では、中小企業診断士2次試験の基礎力を養うために使った書籍(試験対策用参考書を含む)を紹介します。
中小企業診断士2次試験は事例Ⅰ~Ⅳの4つのテーマについて問われる試験で、与えられた与件文と問いに対し、80分間の中で合計約600字程度の論述を解答しなければなりません。
試験時間の中で与件文を読み、解答を考え、解答用紙に書くこととなるため、それぞれの工程で高い精度と速度が求められることとなります。
従って、知識以前にこうした基礎能力を底上げすることが解答の品質向上につながると言えるでしょう。
そこで本記事では主に、
①読む力
②考える力
③書く力
の3つのテーマについて、基礎力を底上げする際におすすめしたい書籍を紹介していきます。
独学で中小企業診断士試験に臨もうとされている方々に向け、本記事が試験対策の一助となれば幸いです。
①読む力
1点目は「読む力」です。
2次試験は厳しい時間制約があるため、いかに解答に必要な情報を抽出してくるかが攻略のカギになります。
しかし、与件文は構造的にまとまっているわけではなく、ある種ナラティブと言いましょうか、時には感情に訴えかけるような情緒的な表現も織り交ぜながら、企業の歴史や現状について臨場感のあるタッチで記述されています。
そこで、重要な部分とそうでない部分を見極め、回答に役立つ情報についてのみを速やかに把握する能力が求められるというわけです。
ただ、そうはいっても与件文はあくまで説明するための文章であり、基本的な文章構造がある程度統一されています。
従って、短い時間の中で読解する上で、構造理解等のテクニックなどは十分に活用可能です。
早く読むためにこそじっくりと論理を学び直すことで、読み違いを防ぎ、読解のスピードを上げるだけでなく、後続の「考える力」「書く力」にも良い影響を与えるだろうと思います。
1. わかったつもり 読解力がつかない本当の原因
中小企業診断士2次試験では架空の企業に対する与件文が提示され、そこに記述されている内容を前提に解答を作成する必要があります。
この与件文、特にフォーマットが決まっているわけではなく、ある種のストーリーテリングのように、設問に関係のない情報も多分に含みながら展開されて行きます。
また、時折出題者の文体のクセというか、少々回りくどい表現が出てくることもあり、速やかに内容を把握する上ではうまく対処する必要が出てくるケースもあります。
特に、過去問などをたくさん問くことの副作用として、過去の似た事例が頭によぎって解釈を誤ってしまうような事故が起きやすくなっていきます。
そのため、いわゆる「読解力」をしっかりと鍛えておくことで、与件文と問題文を先入観なく早く正確に把握することが有効になってきます。
本書は、読解力がつかない「本当の原因」として、実験的データを交えつつメカニズムを解説されています。
著者の西林さんは教育学をご専門とされており、子供の学習論に関わる本を多数出版されています。
「自分はちゃんと読解できている」と思っている方は、特に本書を読んで点検してみてはいかがでしょうか。
個人的に参考になったポイントは以下です。
- 文章における「全体の雰囲気」は、いかに解釈に影響を与えてしまうのか
- なぜ、解釈の間違いに気づけず「わかったつもり」になってしまうのか
- 「わかったつもり」の状態を脱するために心得ておくべきポイントとは
2. 論理トレーニング101題
概要
「論理トレーニング101題」は、野矢茂樹氏による論理思考能力向上のための指南書です。野矢氏は1954年東京都生まれ、東京大学大学院博士課程修了後、多数の著書を発表している哲学者です。
本書は、「議論を読む」と「論証する」の二部構成になっており、接続表現や議論の骨格、論証構造や演繹・推測など、論理的思考を深めるための多様なトピックを網羅しています。
特長
ターゲット読者: 中小企業診断士試験を目指す方や、日常のビジネスシーンでの論理的思考力向上を目指す方に最適です。
問題解決へのアプローチ: 読者のレビューによると、この書籍は単なる理論の羅列ではなく、実際に問題に取り組むことで論理的思考を鍛えることができます。論理トレーニングを通じて、他者への理解を深め、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
実践的な利用法: レビューによれば、前半部分は比較的基本的な問題で構成されており、後半に進むにつれて複雑な概念が登場します。
この段階的アプローチにより、読者は徐々に論理的思考力を高めていくことが可能です。
留意点
本書はかなりアカデミックに近い体裁で展開されていくため、全くの初学者が本書を読むと、難解に感じるかもしれません。
一読で理解できるものではなく、繰り返し読み込んで何度も問題に取り組むことで少しずつ自分のものにしていくイメージで考えるのがおススメです。
学びのポイント
- 論理的思考を鍛えることは、実践のビジネスや日常生活でのコミュニケーションにどのように役立つか?
- 接続詞に着目することで、文章全体の流れをいかにつかむことができるか?
- 論理を鍛え直すことが、なぜ人間関係の質を向上させることにつながるか?
こんな人におススメ
この書籍は、中小企業診断士試験の受験者の中でも特に、問題文の読み違えや読み飛ばしに悩んでいる方にとって有用だろうと思います。
また試験に関係なく、日常業務での論理的思考力を高めたいビジネスパーソンにとってももちろん役立つ内容になることでしょう。
タイトルにある通り、様々な切り口から101題もの問題が用意されているので、これらの問題に腰を据えて取り組むことで、理論だけでは得られない実践的な論理力を身につけることができるでしょう。
まとめ
「論理トレーニング101題」は、論理的思考力を実践的に鍛えることを目指す人々にとって必読の書籍です。
例えば日本語の「接続詞」について、最後に深く考えたのはいつでしょうか?
おそらく、日本語の文法なんて小学校の国語で習ったきりで、日常で不自由なく使えているから深く学び直したことは無い、という人が大半なのではないでしょうか。
私は、本書はそうした方々にとって特に有効であると考えています。
日本語の「論理」について、自分は不自由なく使えているから今さら学び直すのもな、、と思っている方にこそ、まずはセルフチェックの意味で挑戦してみていただくことを強くお勧めします。
読み進めていくうちに自らの知識の「穴」に気づき、ひょっとするとこれが読解の足枷になっていたんじゃないか、というような気付きが1つでもあれば、きっと良い処方箋になるだろうと思います。
3. 思考の質を高める 構造を読み解く力
概要
著者の河村有希絵さんは、東京大学法学部卒業後、ボストン コンサルティング グループに入社し、ノースウェスタン大学ケロッグスクールオブマネジメントでMBAを取得。コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント創業者として、ビジネスパーソンに役立つ「構造の読み解き」を提唱しています。
本書では、構造化思考を通じて論理的思考力と他者理解力を養う方法が紹介されています。
目次は「構造を読み解く力とは何か」「論理を読み解く」「人物の心情を読み解く」「思考を組み立てる」から構成されています。
特長
- 論理的思考力の向上:論理的文章の読解を通して、論理的思考力を鍛えることができます。特に中小企業診断士試験の受験生にとって、論理的な文章解釈能力は重要です。
- 読解力の強化:物語文の読解を通じて、人物の心情を理解し、読解力を高めることができます。
- 実践的なスキル:ビジネスパーソンが直面する複雑な文章や物事を理解し、明確に伝えるスキルを身につけることができます。
この書籍は、論理的思考スキルに課題を抱える中小企業診断士試験の受験生やビジネスパーソンにとって、読解力と論理的思考力を向上させる強力なツールとなるでしょう。
学びのポイント
- なぜ、「論理は言語以上の言語」だと言えるのか?
- 読解力を高めるために、複雑な情報をどのように処理すべきか?
- 構造を読み解く力は、なぜ人の心情を読むことにも役立つのか?
こんな人におススメ
「思考の質を高める 構造を読み解く力」は、論理的思考スキルに課題を抱える中小企業診断士試験受験生や、日々のビジネスで複雑な情報を扱うビジネスパーソンに最適です。
この書籍は、読解力と論理的思考力を強化し、より明瞭で効果的なコミュニケーション能力を身に付けるための実践的なガイドとなるでしょう。
一方で、慣れるまではやや難しく感じる部分もあるかもしれません。それでも、本書の内容を意識しながら継続して読解のトレーニングを進めていくことで、本質を突いた読解力が身についていくはずです。
まとめ
本書によって「構造読解力」について理解を深めることで、日頃の文章を「読む」という行為にあたって常に思考を巡らせることができるようになるでしょう。
また、論理的に考える能力は、同時に他人の心情を読み取る力や効果的に自分の考えを伝える力にも影響を与えます。
そのため、仕事の現場においても成果を最大化する上でも必ず役立つ内容になるのではないかと思います。
②考える力
2点目は「考える力」です。
中小企業診断士2次試験の中では最も時間的比率が短くなってしまいますが、本来的にはこの部分が最も重要な部分となります。
中小企業診断士2次試験の位置づけとして、1次試験の知識を事例に「応用する」ことが求められています。
従って試験中では、1次試験で学んだ知識やフレームワークから必要なものをピックアップし、適切にあてはめていくことが重要な内容になります。
そのためには、フレームワークという抽象的なものに具体的事例をどう結び付けるのか、この部分について自分なりの確固たるロジックを作っておくことが必要です。
1. ロジカル・シンキング (Best solution)
中小企業診断士試験に向けて、論述式問題への対策は重要です。
特に、短い制限時間内に質の高い解答を作成すること、複雑な与件文を整理し効果的な解答を作ること、様々な視点から問題を分析し多面的な論理展開で解答を作ること。これらは容易ではありません。
著書「ロジカル・シンキング」は、こうした課題に対して処方箋になるかもしれません。
本書は、論理的思考とコミュニケーション技術の基礎から応用までを網羅しています。特に注目すべきは、著者が「技術」と定義するロジカルシンキングの方法です。
これには、誰もが訓練を通じて習得可能で、ビジネスの場においても役立つスキルであるという強い信念が込められています。
コミュニケーション技術の習得
本書は、コミュニケーション技術の習得に役立ちます。
自分の考えを論理的に整理し、相手に伝える方法を学べば、説得力のある会話ができるようになります。特に若いビジネスマンにとって有益ですが、中小企業診断士試験を目指す皆さんにも役立つ内容です。
論理的思考のツール
ロジカルシンキングを行ううえでの基本がわかりやすく解説されています。マッキンゼーでよく用いられるMECEやSoWhat?/WhySo?などの考え方が、論理的な解答の構築に役立ちます。
メッセージの3原則
コミュニケーションにおけるメッセージの3原則が定義されており、これがうまく伝わらない、説得できないという問題に対するヒントを提供しています。
課題が明確で、必要な要素を満たした答えがあり、相手にどのような反応を期待するかが明らかであることが、効果的なコミュニケーションには不可欠です。
まとめ
「ロジカル・シンキング」は、中小企業診断士試験の論述式問題対策に役立つだけでなく、ビジネスコミュニケーション全般においても重要なスキルを提供します。
この本を通して、論理的思考を強化し、より効果的な解答を作成することができるようになるでしょう。
個人的に参考になったポイントは以下です。
- コミュニケーションにおいて、相手に伝わるメッセージを作成するための3つの原則は何か?
- 「並列型」と「解説型」の説明をどのように使い分ければコミュニケーションを効果的にすることができるか?
- 複雑な問題を整理する上で、なぜMECEが役に立つか?
2. 武器としての図で考える習慣: 「抽象化思考」のレッスン
概要
著者の平井孝志は、MITスローン経営大学院のMBA保持者であり、筑波大学大学院ビジネスサイエンス系教授です。
本書「武器としての図で考える習慣 「抽象化思考」のレッスン」は、図を使った抽象化思考の方法を紹介します。
この本は、複雑な概念を明確にするための「ピラミッド」「田の字」「矢バネ」といった図式を駆使し、読者に具体的な思考の枠組みを提供します。
特長
この書籍は、特に中小企業診断士試験の対策をしている方や、抽象的なフレームワークと具体的な情報を結びつけたい方に最適です。
本書は以下の点で役立ちます:
- 抽象的な概念を図を使って具体化する技術の習得
- 複雑な問題を分析し、効率的に解決するためのフレームワーク提供
- ビジネスシーンでの意思決定や問題解決のスキル向上
学びのポイント
- 図を使って複雑な概念をどのようにシンプルかつ明確にすることができるか?
- 意思決定や問題解決をどのように迅速かつ効果的に行うことができるか?
- 実践的なビジネスシナリオにおいて、どのようにしてこの書籍の知識を活用することができるか?
こんな人におススメ
「武器としての図で考える習慣」は、抽象的なアイデアや複雑な情報を整理し、明確な構造で捉える方法を探している方に最適です。
特に、中小企業診断士試験の対策をしている方々や、ビジネスシーンでの効率的な意思決定や問題解決を目指す方々には有益な内容です。
まとめ
本書は、ビジネスや学習において抽象的な概念を効果的に扱う方法を提供します。
図を用いた思考のフレームワークは、複雑な情報を整理し、明確な意思決定に導くための強力なツールです。
あなたのビジネスや学習における生産性を高めたいなら、この書籍は必読となるでしょう。
3. 新版 コンサルタントのフレームワーク
皆さんは、1次試験で学んだ理論と2次試験の実践的な事例問題との間にギャップを感じることはないでしょうか?
この書籍は、そのギャップを埋めるための一助となるかもしれません。
概要
「新版 コンサルタントのフレームワーク」は、著者・平賀均氏によるコンサルティングの実務に役立つ指南書です。
早稲田大学卒業後、ビジネススクールを経て中小企業診断士として活躍する著者が、長年の経験をもとにコンサルティングのエッセンスを凝縮しています。
本書は、コンサルタントの基本的なスキルを解説し、具体的かつ実効的な改善提案を目指す「フレームワーク」の重要性を強調しています。
内容は分析手法から具体的なケーススタディまで幅広く扱われており、理論的な知識と実践的な応用をバランスよく学べる構成になっています。
特長
理論と実践のバランス:
中小企業診断士試験の受験者や、ビジネスの理論的な基盤を実際の事例に適用したい方にとって、本書は理論と実践のギャップを埋める一助となるでしょう。
実際のコンサルティング現場でのロジカルシンキング、分析フレームワーク、財務分析など、具体的な手法が豊富かつ詳細に紹介されています。
コンサルティングの深い理解:
著者が提供する多数のフレームワークやケーススタディは、コンサルティングの実際について深い理解を促します。理論のみならず、実際にクライアント企業の課題を解決するための実践的なノウハウを学ぶことができます。
実践的なアドバイスの提供:
コンサルタントとしての役割を理解し、改善提案をどのように行うかについて、本書は有益な洞察を提供します。指導者というよりは相談者としての立場から、簡潔で実行可能なアドバイスの重要性を強調しています。
ただし、本書はあくまでコンサルティングのフレームワークを中心に扱っているため、特定の業界や状況に特化した深い知見を求める方には物足りない可能性があります。
また、前提となる理論的な部分が十分でないと難解に感じられる場合があるかもしれません。
学びのポイント
ロジカルシンキングの実践: MECEやロジックツリーを通じた思考方法が、実践の問題解決を行う上でどのように役立つのか?
分析フレームワークの応用: PEST分析やSWOT分析などの分析フレームワークは、実際のコンサルティングシーンでどのように活用すればよいか?
財務分析の理解: 財務比率分析やキャッシュフロー分析の知識は、なぜ経営判断の根幹を支えるのか?
こんな人におススメ
「新版 コンサルタントのフレームワーク」は、中小企業診断士試験の受験者はもちろんのこと、実際のビジネスシーンで理論と実践を統合したいビジネスパーソンにも最適です。
ビジネスの理論的な基盤と具体的な事例を結びつけることで、より深い理解と実践的なスキルを学ぶことができます。
コンサルティングの基本知識から現場で直面する具体的な課題まで幅広くカバーされているため、様々な目的で読むことができると思います。
まとめ
「新版 コンサルタントのフレームワーク」は、理論から実践への橋渡しとして必読書と言えると思います。
特に、理論的な知識の解説だけでなく、実践的なスキルの面からもコンサルティングに必要な知識と技術がコンパクトにまとまっている点が特長です。
そのため、中小企業診断士の受験者はもちろん、合格後にいざ実践を考える方にとっても有用なものになるかと思います。
③書く力
3点目は「書く力」です。
ご存じの通り、中小企業診断士2次試験は時間制約が厳しい設定となっており、じっくりと推敲を重ねる時間はほとんどの人にとって皆無と言えます。
従って、与件文と設問文からおおよその解答骨子を抽出できた後は、速やかかつ正確に紙上に書き写さなければなりません。
そのため、ある程度の解答フォーマットを事前に用意しておくことは非常に重要な作業となります。
究極的には、設問文の情報のみから大枠の半製品状態の解答が書けるようにしておき、与件文に合わせて虫食いを埋めて完全にするようなイメージで臨めると、現場心理の面からもかなり効果的だと思います。
また、字数制限に合わせて自在に内容を取捨選択できるよう、要約スキルについて鍛え直しておくことも非常に重要です。
要約トレーニングの題材はそれなりに「固い」文章の方が良く、よく進められているのは日経新聞の「春秋」を要約するなどのトレーニング法があります。
ただし、「春秋」は実際の問題と少し乖離があるのと、これといった要約の正解があるわけではないため、手っ取り早く確実にトレーニングしたい場合は専用の本を買ってしまうのが個人的には良いと思っています。
1. EBAメソッドで「読み・解く」合格答案作成講座
概要
本書は中小企業診断士試験対策に新しい風を吹き込むレベルの画期的な一冊です。
江口氏は中小企業診断士であり、EBA中小企業診断士スクールの統括講師として知られています。
本書では、著者の提唱する独自メソッドを用いて、どのようにして効率的かつ効果的に「読み・解く」スキルを身につけるかを、具体的な手順と共に解説しています。
構成は、前半の「習得編」と後半の「実践編」の二つ。習得編では、70点答案を作成するためのメソッドを詳細に解説し、実践編では実際の過去試験問題を用いて具体的な処理手順を学ぶことができます。
特長
- 実践的な学習法: EBAメソッドは、実際の試験状況を想定した実践的な学習法を提供します。これにより、どのような試験問題にも対応できる柔軟性と対応力を身につけることができます。
- 段階的な指導: 本書は、基本的なメソッドの習得から実践的な応用まで、段階的に学べる構成になっています。これにより、読者は自分のペースで効率的に学習を進めることができます。
- 豊富な事例と解説: 実際の過去問題とその解答例を豊富に取り入れ、具体的な解説を加えているため、理論だけでなく実践的な知識も身につけることが可能です。
なお、本書の内容はあくまで中小企業診断士試験の攻略に特化しており、実際の現場に適用するにはややギャップがあるかもしれません。
また、メソッドを詳細に解説するために細かい知識要素の説明は省略されています。
そのため、メソッドを最大限活用するためには、十分な前提知識と継続的学習への意欲は欠かせません。
学びのポイント
- 実践的な解答作成法: 本書の提唱するメソッドによって、どのようにして高得点を安定させられるか?
- 効率的な学習プロセス: 診断士2次試験を効率的に学習する上で、どのようなプロセスを意識すれば良いのか?
- 具体的な事例問題攻略手順: 具体的な解答手順について、限られた時間制約の中でどのような手順を踏めばよいのか?
こんな人におススメ
『EBAメソッドで「読み・解く」合格答案作成講座』は、中小企業診断士試験の準備に苦戦している方、効率的な学習方法を模索している方、そして実践的な解答技術を習得したい方に最適です。
この書籍を読むことで、試験の本質を理解して合格への確実な道筋を示してくれるでしょう。
細部にわたって理詰めで解説されているため、試験の準備に役立つだけでなく、ビジネスシーンでの思考力や問題解決能力を高めるための応用力にも通じる部分があると思われます。
まとめ
あなたが中小企業診断士試験の合格を目指しているなら、『EBAメソッドで「読み・解く」合格答案作成講座』は欠かせない一冊です。
この書籍を読むことで、試験の準備はもちろん、ビジネススキル全般にわたって確実な成長を遂げることができるでしょう。今すぐ手に取り、あなたの合格への第一歩を踏み出しましょう。
2. 中小企業診断士 速修2次テキスト
概要
『速修2次テキスト TBC中小企業診断士試験シリーズ』は、中小企業診断士試験の厳しい挑戦に立ち向かう受験生に最適な参考書です。
著者であるTBC受験研究会主任講師陣はその道のプロで研究に研究を重ねており、受験界隈では非常に定評があります。
この書籍の特徴は、項目ごとの「基礎・A・B・C」の重要度を記載することで、高い網羅性と学習の効率性を両立している点です。
さらに、書籍だけでなく無料講義動画などとの組み合わせにより、学習過程をより効率的かつ理解しやすくしています。
特長
- 実用性と効率性:本書は、中小企業診断士試験の2次試験に特化しており、その難易度の高さを理解した上で設計されています。項目ごとに重要度を明示し、学習の効率化を図っています。
- オンライン学習リソース:YouTube上の無料講義動画を通じて、受験生は自宅での自習をより深く、効果的に進めることができます。これにより、数万円相当の価値がある講義を、実質的に4000円以下で受けることが可能と言えるでしょう。
- ただし、書籍を使用する際の留意点として、独学を前提とした完全な理論の習得のためには、ある程度の基礎知識と自己学習が求められることが挙げられます。
また、書籍のみでは不十分な場合、追加の学習リソースを利用する必要があるかもしれません。
学びのポイント
- 本書が提供する「抽象化ブロックシート」とは一体どういうものなのか?
- 「抽象化ブロックシート」をどのように活用すれば良いのか?
- 受験生が苦戦しがちな事例Ⅳについて、どのように対策を図ればよいのか?
こんな人におススメ
この書籍は、中小企業診断士試験の2次試験対策を探している受験生や、限られた予算内で効果的な学習をしたい人に最適です。
特に、独学での学習を強化したい、または予備校に通うことが難しい受験生にとって、この書籍は必見の資料です。費用対効果の高い教材を求めている方に、『速修2次テキスト』はまさに理想的な選択肢です。
まとめ
『速修2次テキスト』は、中小企業診断士試験の成功を目指すあなたにとって、貴重なリソースとなることでしょう。
この書籍を通じて、試験の知識を深め、自信を持って試験に臨めるようになりませんか? 今すぐ手に取り、次なる学習のステップへと進みましょう。
3. 小論文、レポート、現代文読解に効く! 要約トレーニング問題集
概要
「小論文、レポート、現代文読解に効く!要約トレーニング問題集」は、坂東実子著、まんがびと出版の注目書籍です。
本書は、実際の大学や高校の授業で実践されている要約トレーニングを集約した問題集。文字数に制限のある文書作成のスキルを身につけることができ、大学生や受験生だけでなく、ビジネスパーソンにも役立ちます。
イラスト付きのわかりやすい解説が特徴で、学習を楽しみながら進めることができます。
特長
ターゲット読者: 中小企業診断士試験対策を行う方々、基礎的な要約力を鍛え直し、与件文読解と解答作成のスピードと精度を向上させたい人々に最適。
実践的内容: 大学や高校の授業で実践されている要約トレーニングを基に構成。小論文、志望動機書、就職エントリーシート、会社の報告書など、さまざまな文脈で応用可能。
学習の楽しさを促進: イラスト入りの解説で、より視覚的に理解を深めることが可能。楽しみながら学習できる点は、長期的な学習意欲の維持に寄与します。
書籍を通して、自分の要約スキルを高めることで、どのような改善が見込めるでしょうか?この問題集があなたの目標達成にどのように役立つか、ぜひ検討してみてください。
学びのポイント
- 限られた字数で重要な情報を凝縮する技術は、与件文の読解にどのように役立つか?
- 要約の練習を積むことで、どのように解答作成の質とスピードを上げることができるか?
- 要約という作業は、単に単語をそぎ落とす以外にもどのような方法があるのか?
こんな人におススメ
中小企業診断士試験の受験を控えている方、ビジネス文書やレポート作成において、要約力を鍛えたいと考えている方々には、この書籍で「量」のトレーニングを積むことが近道です。
当然、限られた文字数で効果的に情報を伝える能力は、職場でのコミュニケーション、さらには日常生活での情報整理にも大きな助けとなることは間違いないと言えるでしょう。
まとめ
「小論文、レポート、現代文読解に効く!要約トレーニング問題集」は、要約力の向上を目指すあなたに最適な書籍です。
本書で主に鍛えるべきは、読解した内容を指定した字数に落とし込む情報処理能力だと思っています。
そのため、漫然と解くのではなく、厳しい制限時間や字数制限などを自らに課し、常に高負荷で精度の高い要約力を身に付けることを目標にするのが良いと思います。
また、要約トレーニングを重ねていくことで、「30字ならこのくらいの内容」のように、大まかなワードカウントのセンスが高められるのも一つ大きいと思っています。
実際の試験では、例えば100字以内などで解答を作ると思いますが、解答の構成としていくつかの要素で組み立てることが多いかと思います。
そうした中で「この要素は大体30文字くらいだな」とか、おおよその字数が何となくでもわかるようになるんですね。
これによっていちいち実際にカウントせずに全体の組立てができるようになるので、これも一つ時短につながるだろうと思っています。
いずれにせよ、要約する作業で悩んでいる時間があると非常に効率が悪いので、本書のようなトレーニング本をやりこんでおくことで、試験中に本来時間を使うべき部分に時間を使えるようになることでしょう。
いかがでしたでしょうか。中小企業診断士試験は求められる知識や処理能力に求められる水準が高く、知識以外にも様々なスキルを要し、総合的なビジネス的能力を問われているとも考えられます。
過去問による勉強は当然誰もが行うと思いますが、そこから伸び悩む人が多いのが、本試験の特徴の一つなのではと思っています。
過去問を何周も回しているのになぜか合格水準に達しないという方にとって、本記事で挙げたような基礎的訓練を挟んでみることが有効な場合が多いのではないかと思っています。
本記事の内容が少しでもお役に立てば幸いです。
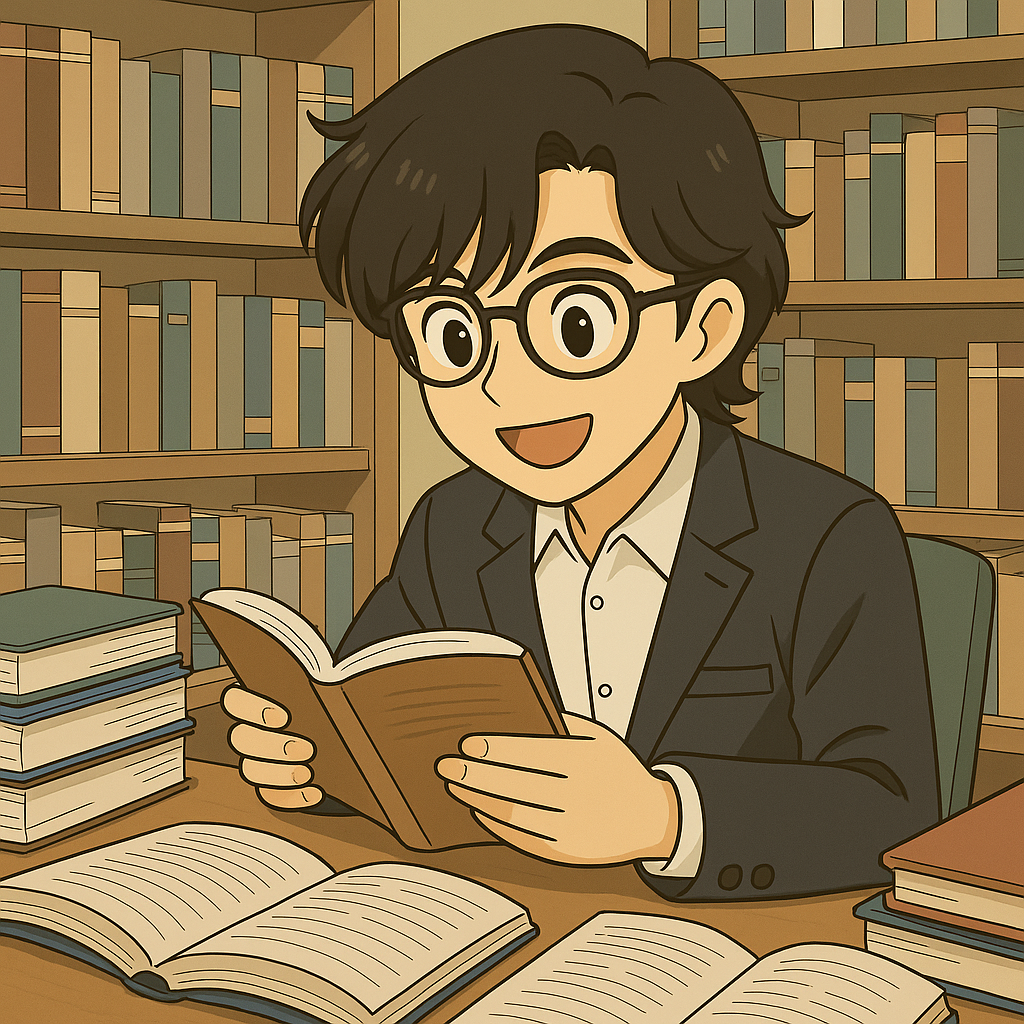









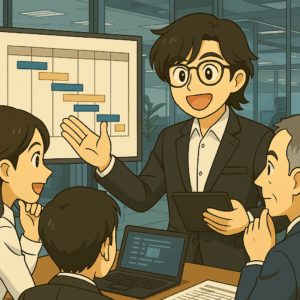
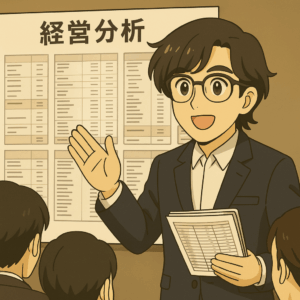
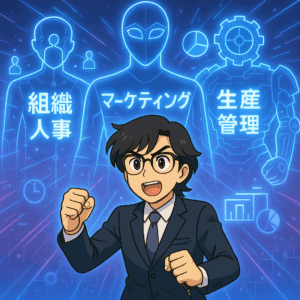


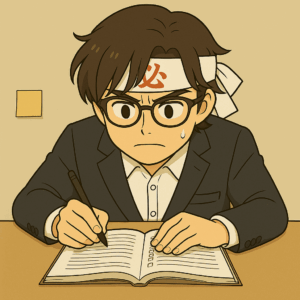
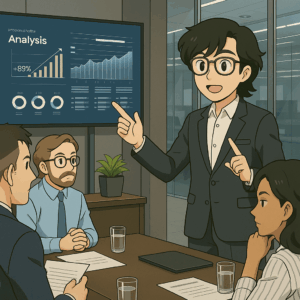
コメント