看護部で外来クラークを4年ほど経験し
2020年より医師事務として転職し、現在は診療情報管理士の資格を目指してます。
このブログでは、主に資格の勉強の記録や医師事務で勉強してきたことなど書いていきます。
「医師事務作業補助者」をめざしたきっかけ
そんな中、前職の看護師長さんから、「『医師事務作業補助者』という資格があるんだけど、知ってる?」といわれ、今自分がやっている業務のプラスアルファのことができると思いチャレンジしてみようと思いました。
これこそ、私が「医師事務作業補助者」を目指すこととなるきっかけとなりました。
思い立ったすぐ後、早速本屋さんに行ってみました。
本屋に行って分かったこととして、この資格に対応した書籍というのがとても少ないということでした。
(後から色々と調べてみて分かったのですが、この資格の受験者は専門学校などの機関で教わっている人の割合が高く、独学での受験者はマイノリティに入るようです。)
ひとまず、定評のある「ステップアップ 医師事務作業補助者学習テキスト」「医師事務作業補助者 演習問題集」の2冊を購入し、勉強を開始しました。
最初のうちはとりあえずテキストを1周読み、大事そうなところには線を引いたり、ノートに書き写したり、問題を解いてみるなどしてみました。
ですが、自分にとっては実技の問題が難しく特に診療情報提供書を作成する問題などは本当に苦戦しました。
特に、主病名の経過を簡潔にまとめるのが難しく、初回受験時は学科はクリアできたものの実技で落ちてしまいました。。
あきらめずに再チャレンジ!
しばらく書店で買った書籍のみで勉強を続けていました。
しかし、買った書籍のみでは実技の対策が難しく、限界を感じるようになりました。
そこで、書籍以外の方法が無いかどうか考え始めました。
そんな中で見つけたのが「TERADA 医療福祉カレッジ」という会社の通信講座でした。
この講座を受講し、自分が苦手な実技の問題をひたすら何回も解くことで、何とか合格レベルまで達することができました。(これは後々、働いたときに役に立ちました!)
私が受験した「全国医療福祉教育協会」の医師事務作業補助者の試験は年に3回ほど受験可能です。
振り返ると、めげずに試験を受け続け、実直に傾向を掴んでいったことが最終的に合格につながったと思います。
そして転職
資格の存在を教えてくれた師長さんには申し訳ないと思いつつも、せっかく医師事務の試験で合格できたのと、前職に勤めていた病院では医師事務として勤めている方がいらっしゃらなかったため
新天地で医師事務の経験が豊富な方から教えを請いたく、2020年に転職し現在に至ります。
次なる目標「診療情報管理士」
転職してからは1年経つのはあっという間でした。
仕事の細々としたことを覚えなければならないのと、循環器科のは配属が決まったものの前職の外来クラークよりも入院やカテの予約入院が決まったらすぐに検査の予定を立てたりと、常に先生と心理的にも物理的にも近い距離で働いているため疾患に少しは詳しくなる必要がありました。
毎日というわけではないですが、カンテキという循環器の本など読みつつ、書類やカルテを書くの業務にも追いつきたかったので、もう一度医師事務の教科書を開きなおして復習の日々でした。
循環器科の業務に携わる中で、将来的な異動の機会に備えるために他の疾患のことについても勉強したいなと思う様になりました。
そのため、現在は診療情報管理士の資格取得を目指して日々勉強を続けています。
こちらの経験談についても、いつか記事にできたらと思います。
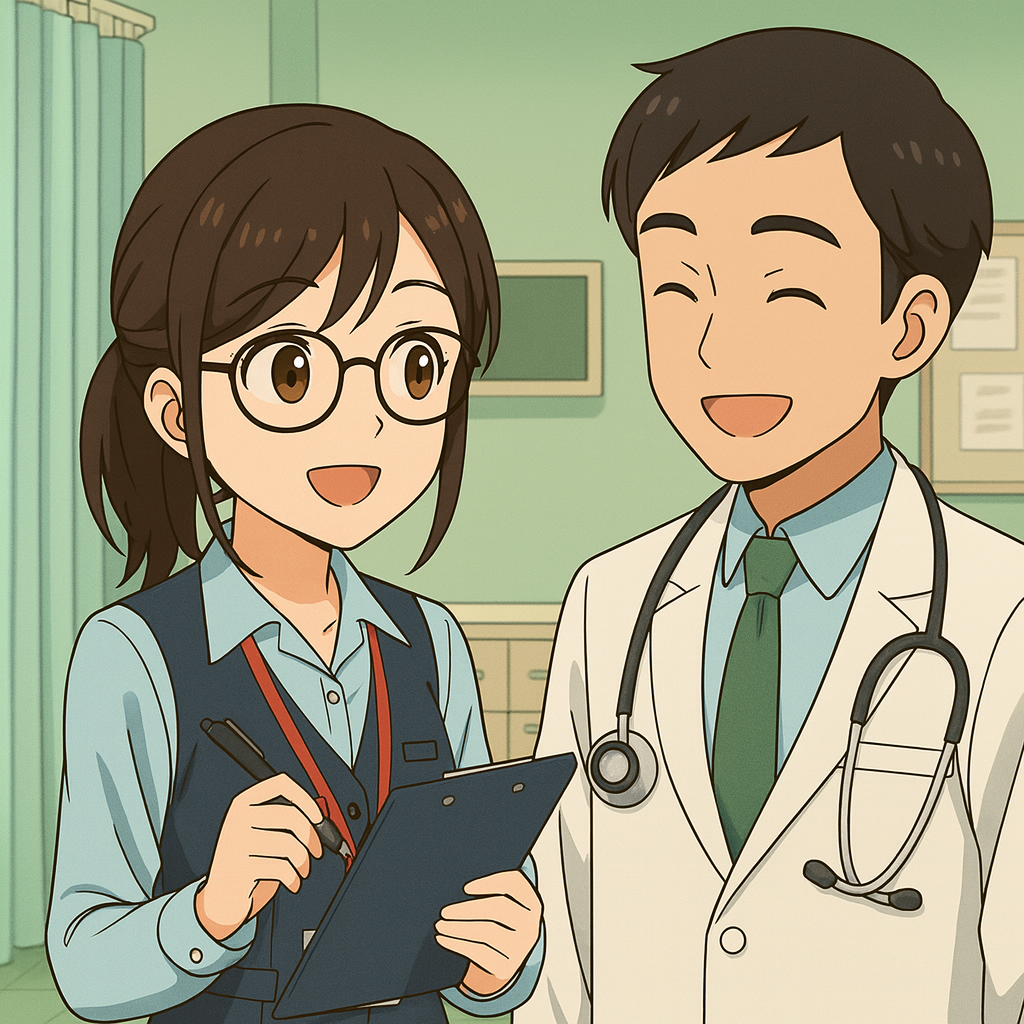


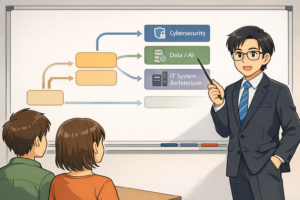
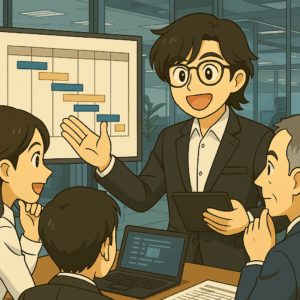
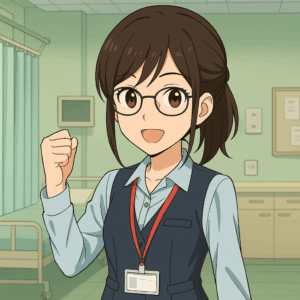


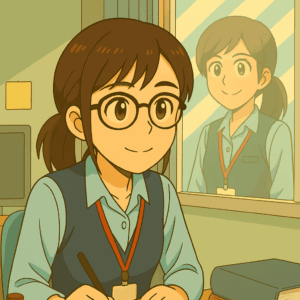
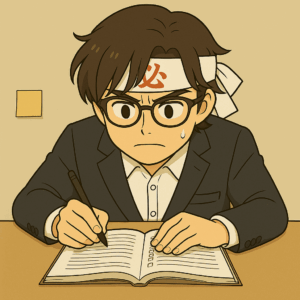
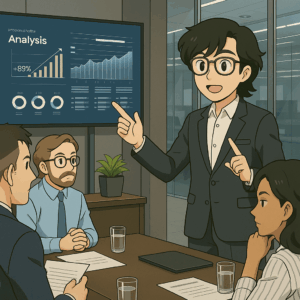
コメント